はじめに
最近、「ファスティング(断食)」という言葉を耳にする機会が増えています。
美容やダイエットのために実践する人も多いですが、実はその効果の本質は生物学的メカニズムにあります。
断食は、単なる「食べない」行為ではなく、細胞がストレスに適応し、生命維持システムを再起動するプロセスです。
この記事では、断食が体にどのような影響を与え、どんな分子・遺伝子レベルの変化が起こるのかを、科学的な視点でわかりやすく解説します。
1. エネルギー代謝のスイッチ:グルコースからケトン体へ

断食を始めて約12〜24時間後、体内のグリコーゲンが枯渇し、肝臓は脂肪酸を分解して**ケトン体(β-ヒドロキシ酪酸など)**を産生します。
この切り替えを「代謝スイッチ」と呼びます。
- 通常:ブドウ糖 → ATP生成(解糖系)
- 断食中:脂肪酸 → ケトン体 → ATP生成(β酸化)
この代謝転換により、脳もエネルギー源をグルコースからケトン体に切り替えます。
ケトン体は単なる燃料ではなく、抗酸化作用・抗炎症作用を持つ「シグナル分子」としても働きます。
特にβ-ヒドロキシ酪酸は、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)を阻害し、遺伝子発現を変化させるエピジェネティックな効果をもたらすことが知られています。
2. オートファジーの活性化:細胞が自らを掃除する時間

断食の最大の特徴の一つが、**オートファジー(autophagy)**の活性化です。
これは、細胞内の古いタンパク質や壊れた細胞小器官を分解し、再利用する仕組みです。
断食によって栄養センサーであるmTOR(mechanistic Target of Rapamycin)の活性が低下し、代わりにAMPKが活性化します。
AMPKはエネルギー不足を感知してオートファジーを誘導し、不要な成分をリサイクルして新たなエネルギーを得ます。
このプロセスは、
- 神経細胞の保護(アルツハイマー病の予防)
- 老化した細胞の除去
- 免疫細胞のリフレッシュ
などに寄与します。
つまり断食は、細胞の「大掃除」期間を与える行為なのです。
3. ミトコンドリアの再構築と酸化ストレスの低減
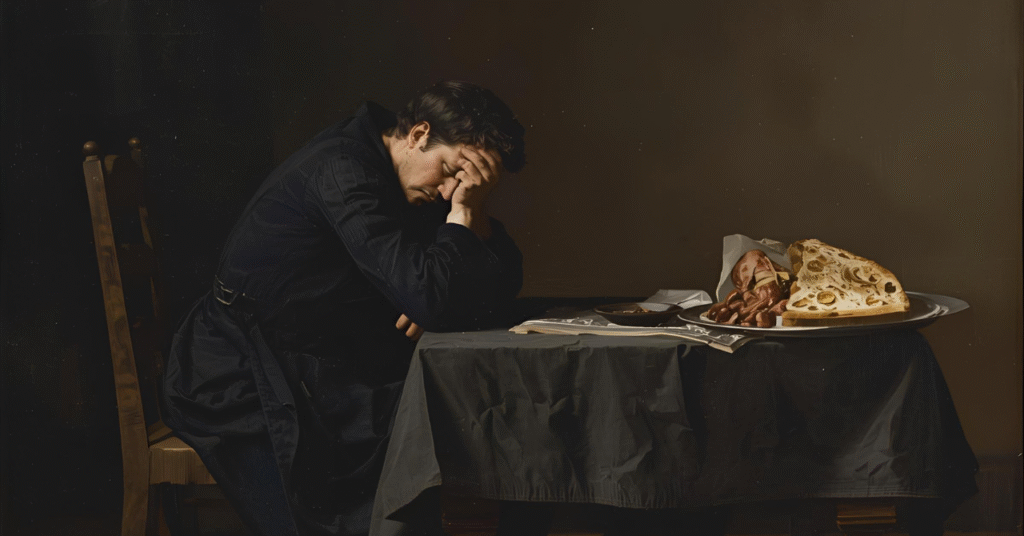
断食中、細胞はエネルギー産生を最適化するためにミトコンドリアの動態を変化させます。
古いミトコンドリアは選択的に除去され(ミトファジー)、新しいミトコンドリアが生まれます。
また、断食によって一時的に軽度の酸化ストレスが発生しますが、これは細胞に「適応的ストレス応答(ホルミシス)」を引き起こします。
ホルミシスとは、「少しのストレスが細胞を強くする」という現象です。
この結果、**抗酸化酵素(SOD、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなど)**が増加し、長期的には酸化ダメージを減らします。
4. 遺伝子発現の変化と寿命延長への影響

断食は、単にエネルギー源を変えるだけでなく、遺伝子レベルのスイッチを切り替えます。
特に関与が知られているのが以下の分子群です:
- SIRT1:長寿遺伝子。NAD⁺依存的脱アセチル化酵素。
- FOXO3:ストレス応答を制御し、抗酸化・DNA修復に関与。
- PGC-1α:ミトコンドリアの新生を促進。
これらの遺伝子が活性化されることで、老化抑制・代謝改善・DNA修復促進などが起こります。
マウス実験では、断食やカロリー制限によって寿命が延びることが複数報告されています。
つまり、断食は「生物学的な若返り」を促す要素を備えているのです。
5. 腸内細菌叢の変化と免疫系の再編成

断食は腸内細菌の組成にも大きな影響を与えます。
食事が途絶えると、一部の腸内細菌が減少し、代わりに**短鎖脂肪酸(特に酪酸)**を産生する善玉菌が増加します。
酪酸は腸の上皮細胞のエネルギー源であり、炎症抑制・免疫バランス維持に重要です。
また、断食は腸管バリア機能を改善し、免疫細胞(特に制御性T細胞)の働きを整えることも知られています。
このように、腸内環境の再構築を通して全身の免疫状態がリセットされるのです。
6. 成長ホルモンと幹細胞の活性化:再生のタイミング
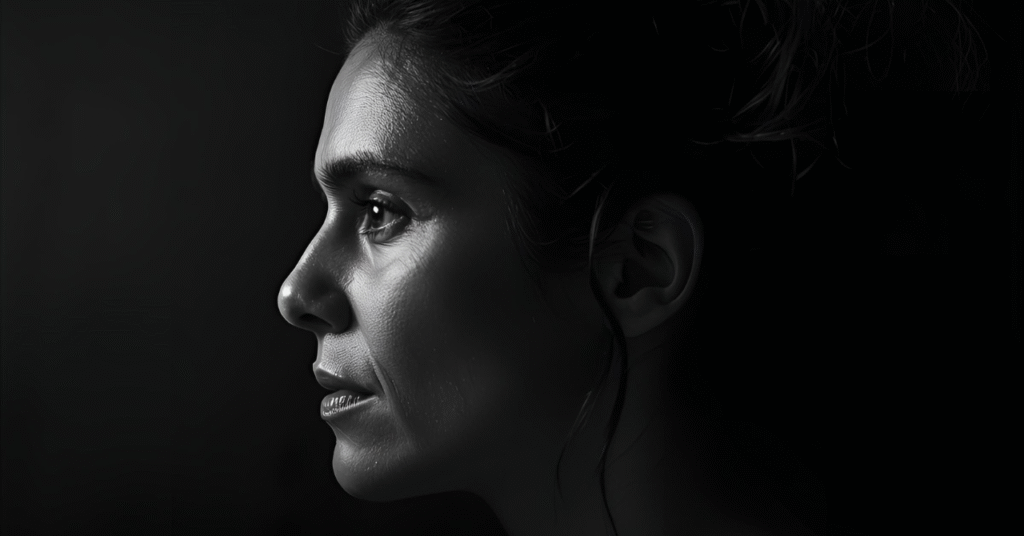
断食中は、意外にも**成長ホルモン(GH)**の分泌が増加します。
特に24時間以上の断食で顕著になり、筋肉の分解を防ぎながら脂肪代謝を促進します。
さらに、マウス実験では断食によって造血幹細胞の再生が誘導されることが報告されています(Valter Longoらの研究)。
つまり、断食は「再生スイッチ」を押す行為でもあるのです。
これは単に体重を減らすだけでなく、細胞レベルで体を作り直す生物的再構築といえます。
7. 脳機能の向上と神経可塑性

断食は脳にも大きな影響を与えます。
断食中に分泌されるケトン体や神経栄養因子(特にBDNF:脳由来神経栄養因子)は、
- 記憶力や集中力の向上
- シナプスの新生促進
- 神経細胞の保護
に関与します。
また、軽度のエネルギー不足は神経細胞に「生き残り反応」を引き起こし、
ニューロンの耐性や可塑性を高めることがわかっています。
一種の「脳トレーニング」効果が断食によって自然に発生するのです。
まとめ:断食は「細胞の再起動」だった
断食は、単なるダイエット法ではなく、生物が進化の過程で備えたサバイバル機構を活性化する行為です。
細胞は飢餓を「危機」ではなく「再構築のチャンス」として利用します。
断食による主な効果まとめ
- ✅ グルコースからケトン体への代謝転換
- ✅ オートファジーの活性化
- ✅ ミトコンドリアの再生と抗酸化作用
- ✅ 遺伝子発現の調整(SIRT1・FOXO3など)
- ✅ 腸内細菌叢と免疫系のリセット
- ✅ 幹細胞の活性化と再生促進
- ✅ 脳の神経可塑性と認知機能向上
現代社会では常に「食べ過ぎ」が当たり前ですが、
断食は細胞が本来持つ生命維持プログラムを再び動かすための生物学的スイッチなのです。
参考文献
- Longo, V.D. & Panda, S. (2016). Fasting, Circadian Rhythms, and Time-Restricted Feeding in Healthy Lifespan. Cell Metabolism.
- Madeo, F. et al. (2019). Fasting-Mimicking Diet and Cellular Stress Resistance. Nature Reviews Molecular Cell Biology.
- Levine, M.E. et al. (2014). Low Protein Intake is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 and Younger but not Older Population. Cell Metabolism.
- De Cabo, R. & Mattson, M.P. (2019). Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. New England Journal of Medicine.



