はじめに
「人間の言葉を理解できるのはヒトだけ」——長らくそう考えられてきました。
しかし、2025年に発表された最新の神経科学研究によって、アシカの脳が人間の言葉を意味レベルで処理している可能性が示唆されました。
この発見は、「動物の知能」の常識を揺るがすだけでなく、言語の起源や進化を考える上でも重要な意味を持ちます。
本記事では、この最新ニュースをもとに、アシカの脳と“ことば”の関係を3つの側面から詳しく解説します。
1.アシカの脳が言葉を「音」ではなく「意味」で認識している?

研究チーム(米・カリフォルニア大学)は、訓練されたカリフォルニアアシカに対して、特定の単語を聞かせながらfMRI(機能的磁気共鳴画像法)で脳活動を測定しました。
結果:
- 「ball(ボール)」や「fish(魚)」など、対象を意味する単語に対して脳の側頭葉が反応。
- 同じ音節構造を持つ無意味語(例:”balp”)では反応が弱い。
つまり、アシカの脳は単なる「音のパターン」ではなく、“意味カテゴリー”としての理解をしている可能性があるのです。
これは、人間の言語処理に関わるウェルニッケ野に類似した領域が、海の哺乳類にも存在することを示唆しています。
2.アシカの驚くべき学習能力と記憶力

アシカは古くからサーカスなどで“賢い動物”として知られてきました。
しかしその知能は「芸を覚える」レベルにとどまらず、文法的なパターンの学習にも及ぶことが実験で確かめられています。
研究例:
- 単語の並び替えを訓練すると、「A-B-C」という構造を他の単語にも応用できる。
- 音の系列を再現する能力は、霊長類よりも高いケースがある。
このような結果から、アシカは「音の連続」ではなく、「構造や関係性」を学習していると考えられています。
つまり、彼らの学習メカニズムは**“言語の原型”**に近い構造を持っている可能性があるのです。
3.水中生活とコミュニケーション進化の関係
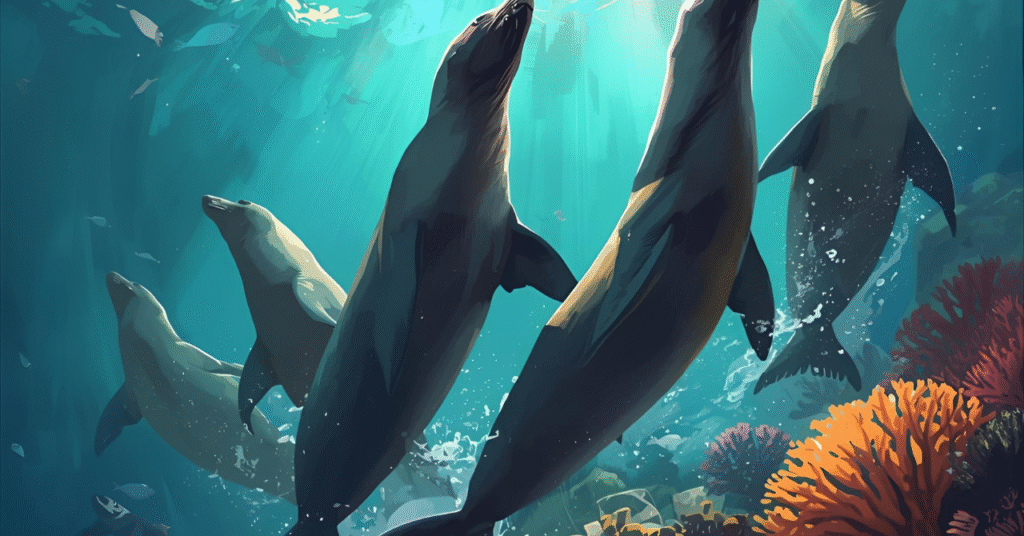
興味深いのは、アシカやイルカなど水中生活をする哺乳類に、言語的な理解能力が多く見られることです。
なぜ水中動物に“言葉のような知能”が発達したのでしょうか?
進化的な仮説
- 音が主な情報手段だから:水中では視覚が制限されるため、音によるコミュニケーションが中心。
- 群れ行動が発達したため:社会的な連携のために“意味のある音”を共有する必要があった。
- 長距離伝達の必要性:遠くの仲間と意思疎通するために、音の複雑化が進んだ。
こうした背景から、水中哺乳類の脳は音の「文法」や「意味」処理に特化して進化した可能性があります。
4.ヒトの言語進化を探る“鏡”としてのアシカ

この研究の意義は、単に「アシカが賢い」という話ではありません。
むしろ、人間の言語がどのように誕生したかを探る“進化の鏡”として重要なのです。
考えられる仮説
- ヒトと言葉を共有できる基盤(神経回路)は、共通の哺乳類祖先にすでに存在していた。
- 言葉の起源は「ヒト固有」ではなく、社会性と音声認識能力の融合から生まれた。
つまり、アシカは“言葉の起源の証人”ともいえる存在なのです。
5.今後の研究と応用の可能性

この分野の研究はまだ始まったばかりですが、今後は次のような応用が期待されています。
応用の可能性
- 動物との新しいコミュニケーション技術(AI音声認識×行動学)
- 言語障害リハビリへの応用(脳の意味処理モデルの比較)
- 水生哺乳類の保全研究(音によるストレス評価や意思伝達解析)
特にAI技術の発達によって、「人間以外の言語的コミュニケーション」の研究は新時代に突入しています。
まとめ
アシカが人間の言葉を“意味として理解する”という発見は、単なる好奇心を超えた科学的意義を持ちます。
それは「知能とは何か」「言葉とは何か」という根本的な問いに、新しい視点を与えるものです。
アシカの脳は、静かな海の中で私たちに語りかけています。
参考
- Nature Communications (2025) “Semantic processing in California sea lions”
- カリフォルニア大学海洋神経科学研究所 発表資料
- NHKニュース「アシカが人間の言葉の意味を理解?脳活動の新発見」


