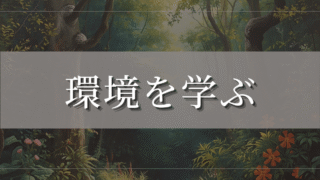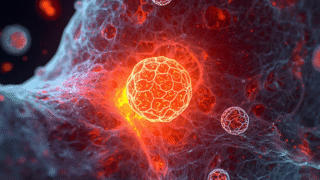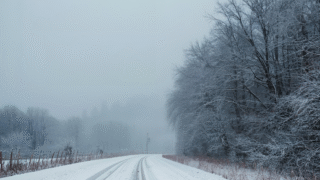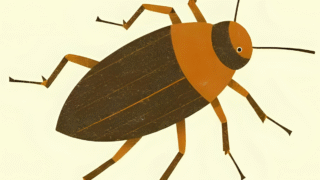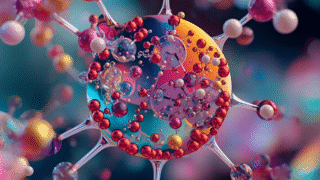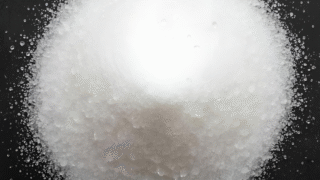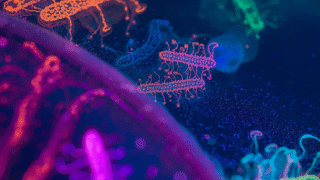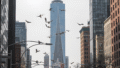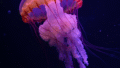はじめに:外来種ってそもそも何?
外来種とは「本来その地域にはいなかったのに、人間の活動によって持ち込まれた生物」のこと。
世界的に生物多様性を脅かす大きな要因の一つとされ、地球規模での環境問題 にも関わっています。
ここでは、外来種について知っておくべきポイントを7つにまとめました。
「アライグマやブラックバスくらいしか知らない」という人も、読み終える頃には街を歩く目が少し変わるはずです。
1. 外来種は「悪者」ではなく、人間が運んできた存在

外来種が問題になると「生物が悪い」と思いがちですが、実際にはほとんどが人間の活動によって持ち込まれています。
ペットとして輸入されたものが逃げ出したり、観賞用に持ち込まれた植物が広がったり、貨物に紛れて侵入したり…。
つまり外来種問題は、人間活動の副産物 といえます。
2. 日本は外来種が入りやすい国

日本は島国だから外来種の影響を受けにくいと思われがちですが、実は逆。
港や空港が多く、輸入食品・観葉植物・ペットの流通も盛んなため、外来種が入り込みやすいのです。
外来生物法で規制されている生物は 153種以上(2025年時点) にのぼります。
3. 有名な外来種:アライグマ・ブラックバス・セイタカアワダチソウ

外来種問題と聞いてよく挙げられる例がこちら:
- アライグマ:ペットとして輸入 → 野生化 → 農作物被害や在来種への影響。
- ブラックバス:釣り目的で導入 → 在来魚を捕食し、湖や川の生態系を変化させる。
- セイタカアワダチソウ:観賞用に導入 → 強力な繁殖力で在来植物を駆逐。
これらは「外来種=問題生物」というイメージを広めた代表格といえます。
4. 実は身近な外来種:公園や庭にも
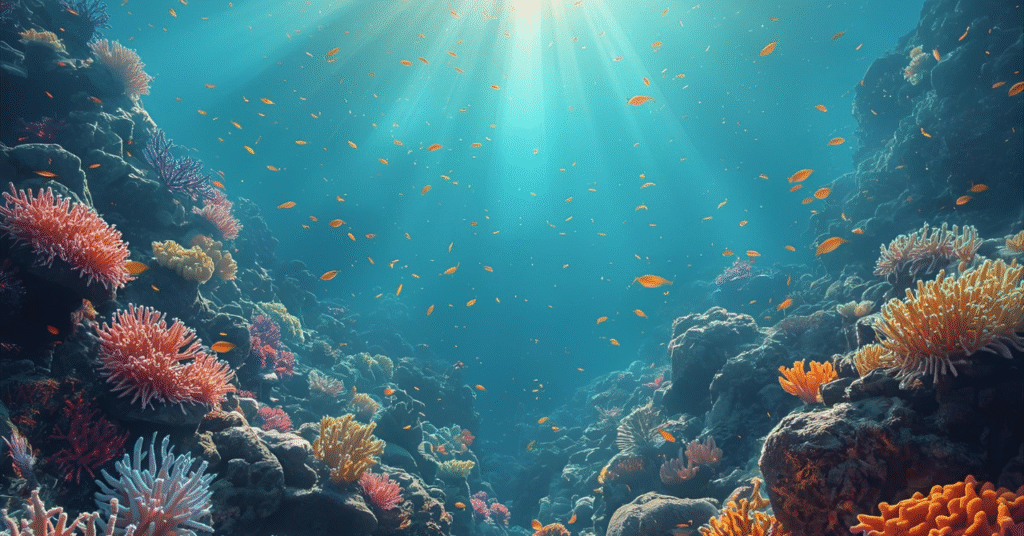
「外来種なんて田舎の話でしょ?」と思ったら大間違い。
都市の公園や庭先にも外来種は潜んでいます。
- アカミミガメ(ミドリガメ):夏祭りのカメすくい → 飼えなくなって池に放され野生化。
- ナミテントウ:海外から侵入し、在来のテントウムシを駆逐するケースも。
- ヒメジョオン:白い花を咲かせる外来植物。街中でもよく見かけます。

「あれ?うちの近所のあの花も外来種だったの?」という発見があるはずです。
5. 外来種が与える影響は3つの面で深刻

外来種は「生態系」だけでなく、「農業」「人間の生活」にも影響します。
- 生態系への影響:在来種の捕食・競合による絶滅リスクの増大。
- 農業への影響:畑を荒らすアライグマ、田んぼを荒らすウシガエルなど。
- 人間への影響:セアカゴケグモなど毒を持つ外来種が増える危険。
外来種問題は「自然保護」だけでなく、私たちの生活とも直結しているのです。
6. 駆除だけでは解決しない?

外来種対策というと「駆除」をイメージしますが、現実には完全駆除はほとんど不可能です。
むしろ近年では「共存」を前提とした研究も増えてきています。
- 市民が参加して外来種を調べる「市民科学」プロジェクト
- 生態系への影響を最小限にする「管理型共存」
- 生息範囲を限定して影響を抑える方法
外来種問題は単純に「排除すべきか」ではなく、どう付き合うか が課題となっています。
7. 私たちにできること

「外来種の問題って、結局は行政や研究者がやることじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。
でも実際には、一般市民の意識が非常に大切です。
- ペットや観賞用植物を「捨てない」
- 散歩や釣りのときに外来種を見つけたら報告する
- 外来種問題に関する知識を家族や友人にシェアする
小さな行動が積み重なって、未来の生態系を守ることにつながります。
おわりに:外来種は「人間の鏡」
外来種はただの「迷惑な侵入者」ではなく、人間の行動の結果を映し出す鏡 でもあります。
アスファルトの隙間に咲く雑草を見る目が変わるように、外来種を見る目も変わると、街の風景がまた違って見えてくるはずです。