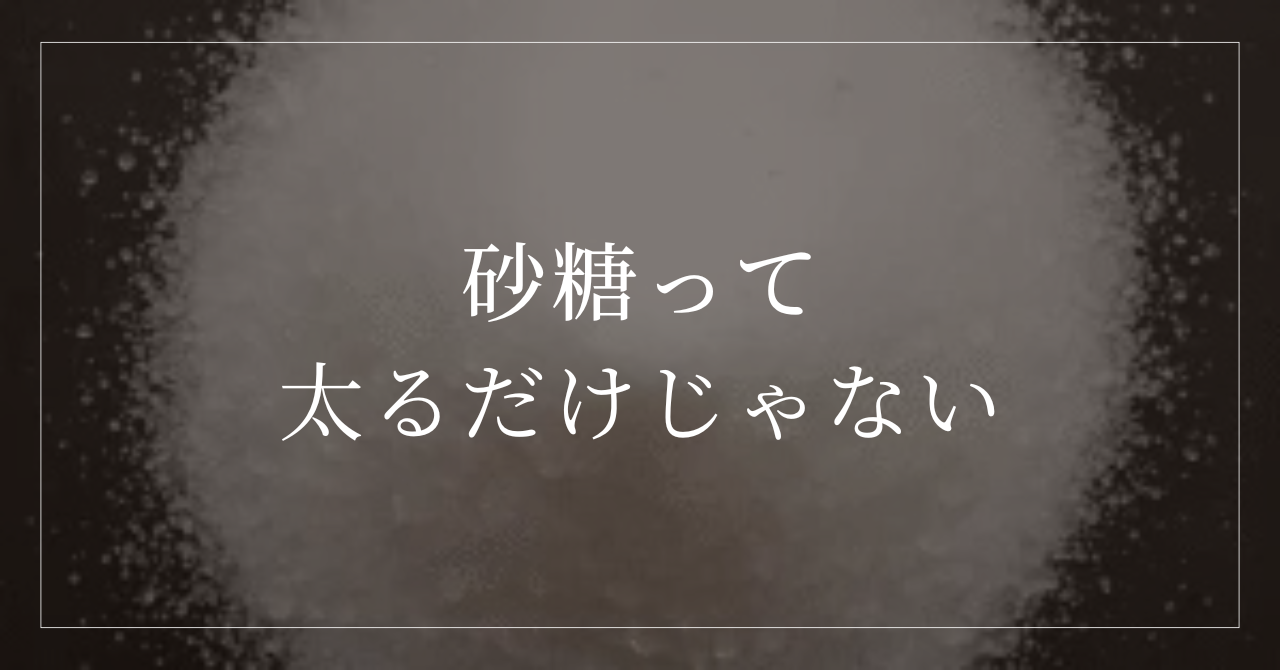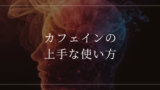- はじめに|甘いものを食べたあと、こんな不調ありませんか?
- 結論|砂糖の問題は「量」と「摂り方」にある
- なぜ太りやすくなる?|脂肪を溜め込む仕組み
- 疲れやすい・集中できない理由|血糖値のジェットコースター
- 肌が老けて見える原因|糖化という見えない変化
- なぜ「やめられない」のか|砂糖の依存性
- 虫歯・口臭リスクも無視できない
- じゃあ、どうすればいい?|現実的な5つの対策
- まとめ:砂糖と上手に付き合おう
- 砂糖対策の選択肢として考えられるもの
- 参考文献
- ある前提から話します
- 体は「甘さ」をどう認識しているのか
- 血糖値の乱高下が本当に壊しているもの
- 糖化は「老化物質が増える現象」ではない
- 炎症との関係は、もっと深い
- 依存は「脳が壊れる」話ではない
- ゼロにしない、という戦略の意味
- 現実的に効いてくる介入ポイント
- 最後に:砂糖は敵ではない
はじめに|甘いものを食べたあと、こんな不調ありませんか?
「甘いものを食べたあと、なぜかだるくなる」
「集中力が切れやすい」
「最近、肌の調子が落ちてきた気がする」
もし心当たりがあるなら、その原因は砂糖の摂りすぎかもしれません。
砂糖はエネルギー源として必要な栄養素ですが、”現代の食生活では“気づかないうちに過剰になりやすい”のが問題です。
この記事では、
- なぜ砂糖の摂りすぎで体調や肌に影響が出るのか
- 生物学的に体の中で何が起きているのか
- 完全にやめなくてもできる、現実的な対策
を、専門知識をかみ砕いて解説します。
結論|砂糖の問題は「量」と「摂り方」にある
砂糖そのものが即座に悪いわけではありません。
問題は、
- 血糖値を急激に上げる形で摂っていること
- 日常的に「過剰」になっていること
この2点です。
体は急激な変化が苦手です。
砂糖を一気に摂ることで、体内のバランスが崩れ、さまざまな不調として現れます。
なぜ太りやすくなる?|脂肪を溜め込む仕組み
何が起きているのか
砂糖を多く含む食品(清涼飲料水・お菓子など)を摂ると、血糖値が急上昇します。
すると体はインスリンを大量に分泌し、余った糖を脂肪として保存しようとします。
これは「非常時に備える」ための正常な反応ですが、頻繁に起きると脂肪が溜まりやすくなります。
さらに問題になる点
精製された糖(特に果糖)は腸のバリア機能を弱めることが報告されています(Nature Communications, 2020)。
腸の防御壁が弱ると、慢性的な炎症や体調不良につながる可能性があります。
脂肪についてはこちらから
疲れやすい・集中できない理由|血糖値のジェットコースター
結論から言うと
砂糖は「一時的に元気になるが、反動が大きい」エネルギー源です。
体の中では
血糖値が急上昇 → インスリンで急降下
この乱高下が起こると、
- 強い眠気
- イライラ
- 集中力の低下
が起きやすくなります。
この状態が続くと、インスリン抵抗性(糖尿病予備軍)につながることもあります。
肌が老けて見える原因|糖化という見えない変化
砂糖を摂りすぎると、体内で糖化(AGEsの生成)が進みます。
これは、糖がタンパク質と結びついて劣化させる反応です。
肌で言えば、
- コラーゲンが硬くなる
- ハリや弾力が失われる
といった変化につながります。
スキンケアだけでは改善しにくい理由は、体の内側で起きている反応だからです。
なぜ「やめられない」のか|砂糖の依存性
砂糖を摂ると、脳内でドーパミンが分泌されます。
これは快感や報酬に関わる物質で、依存性が指摘されています(Yale Journal of Biology and Medicine, 2010)。
その結果、
- もっと欲しくなる
- 量が増えていく
- やめようとするとストレスを感じる
という悪循環に入りやすくなります。
虫歯・口臭リスクも無視できない
砂糖は口腔内の細菌のエサになります。
細菌が作り出す酸が歯のエナメル質を溶かし、虫歯や歯周病の原因になります。
これは子どもだけでなく、大人でも同じです。
じゃあ、どうすればいい?|現実的な5つの対策
完全にやめる必要はありません。
- 清涼飲料水を水・お茶に置き換える
- 間食は甘いお菓子 → ナッツや果物に
- 加工食品の成分表示を見る習慣をつける
- 調味料の「隠れ砂糖」に注意する
- 「減らす」意識を持つ(ゼロにしない)
まとめ:砂糖と上手に付き合おう
砂糖は完全に排除すべきものではありません。
ただし、無意識に摂りすぎている人が非常に多いのも事実です。
「なんとなく不調」の原因を、食習慣から見直す。
それだけでも体は少しずつ変わっていきます。

今回この記事を書くにあたってこの本を参考にしました。
砂糖対策の選択肢として考えられるもの
「甘いものを完全に我慢するのは難しい」という人も多いと思います。
実際に使われている選択肢としては、
- 血糖値の上昇が比較的緩やかな甘味料
- 食後の血糖値対策を意識したサプリメント
などがあります。
※体質や目的によって合う・合わないがあります。
※あくまで生活習慣の補助として考えるのが前提です。

実は血糖値(インスリン)に関してはカフェインと強いかかわりがあります。カフェインを取ることでインスリン恒常性をコントロールできると考えられています。
参考文献
- Nature Communications (2020)
- British Journal of Psychiatry (2017)
- Yale Journal of Biology and Medicine (2010)
甘いものを控えているのに、
なぜか疲れやすい、老けた気がする、集中できない。
それは「意志」や「体質」の問題ではありません。
砂糖が体内でどんな信号を出しているのかを、ほとんどの人が知らないだけです。
有料部分では、
・血糖値の乱高下が脳と自律神経に与える影響
・糖化が「老化物質」ではなく「修復不能な損傷」である理由
・砂糖が炎症を“長引かせる”仕組み
を、生物学の視点で整理しています。
我慢ではなく、理解からコントロールしたい人へ。