はじめに
庭先や畑で見かける、アリがアブラムシの群れを「なでる」ような光景──これは単なる偶然ではなく、長年にわたる進化が生んだ「共生」(トロフォビオーシス:trophobiosis)です。アリはアブラムシが分泌する甘い「蜜」=ハニーデューを得る代わりに、捕食者や寄生蜂からアブラムシを守り、時には移動・配置まで行います。この「小さな農業」は生態系や農作物被害にも直結するため、基礎生態学から実用的な防除まで幅広い関心を集めています。
1. アリとアブラムシの基本 — どんな種類が関わるのか
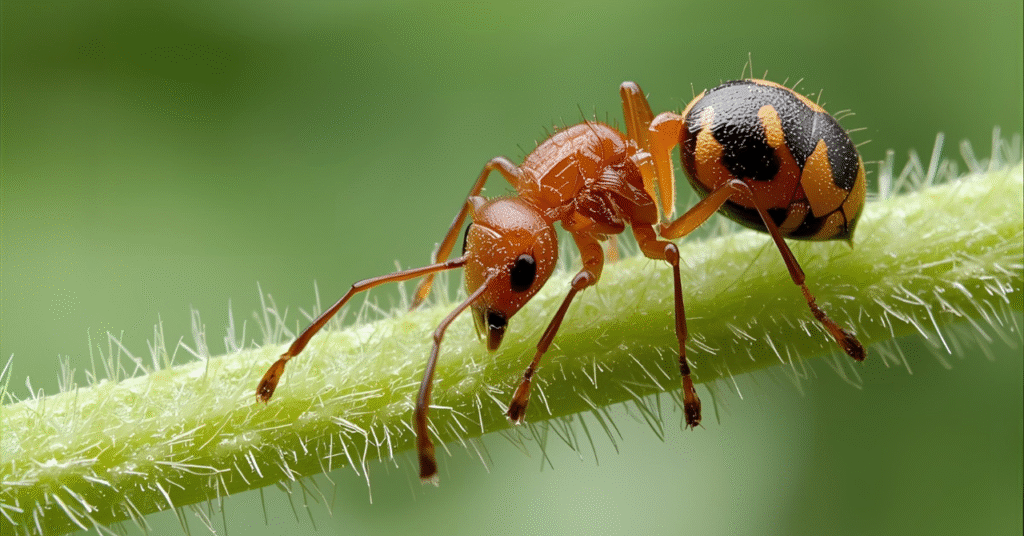
アブラムシ(カメムシ目アブラムシ科など)は植物の師部(フロース)を吸って生活し、余剰糖をハニーデューとして排出します。一方、ハニーデューを好むアリは世界中の多数種がこれを利用し、アブラムシとの相互作用を築いてきました。全てのアブラムシがアリに守られるわけではなく、種や生息環境によって関係の強さは大きく異なります。例えば地中や根に棲む「根アブラムシ」を専属的に育てるアリ属も知られています。
2. 共生(トロフォビオーシス)の仕組み — 「飼育・保護・移動」の三役

この共生の主要要素は次の通りです。
- 栄養供給(アブラムシ→アリ):ハニーデューは糖類を豊富に含み、アリの重要な炭水化物源になります。
- 防御(アリ→アブラムシ):アリは捕食者(テントウムシやヒメバチなど)を排除し、アブラムシの生存率を上げます。結果としてアブラムシ個体数・群密度が増え、植物への影響も大きくなることがあります。
- 移動・配置(アリの管理):観察例ではアリがアブラムシを植物の“高生産”部位へ移す、あるいは寒冷期に巣穴へ連れて行く例が報告されています。つまりアリは単なる“採取者”ではなく、積極的な「農場管理者」と言えます。
3. 化学コミュニケーションと行動操作 — フェロモンと糖の力

共生は化学的なやり取りで支えられています。ハニーデューの糖組成(例:メレジトース=melezitoseなどの三糖の含有量)がアリの嗜好を左右し、アリは糖組成の良いアブラムシを優先して保護します。ハニーデューの質はアブラムシ種だけでなく、寄主植物やアリの影響で変化することが知られます。さらに、アリが放つ化学シグナルはアブラムシの行動や発達(翅の発生・飛散行動)に影響を与え、分散を抑えることで“飼いやすい”集団を維持する可能性があります。これらは共生の安定性や進化に深く関わります。
4. 生態系と農業への影響 — 「益」か「害」か?
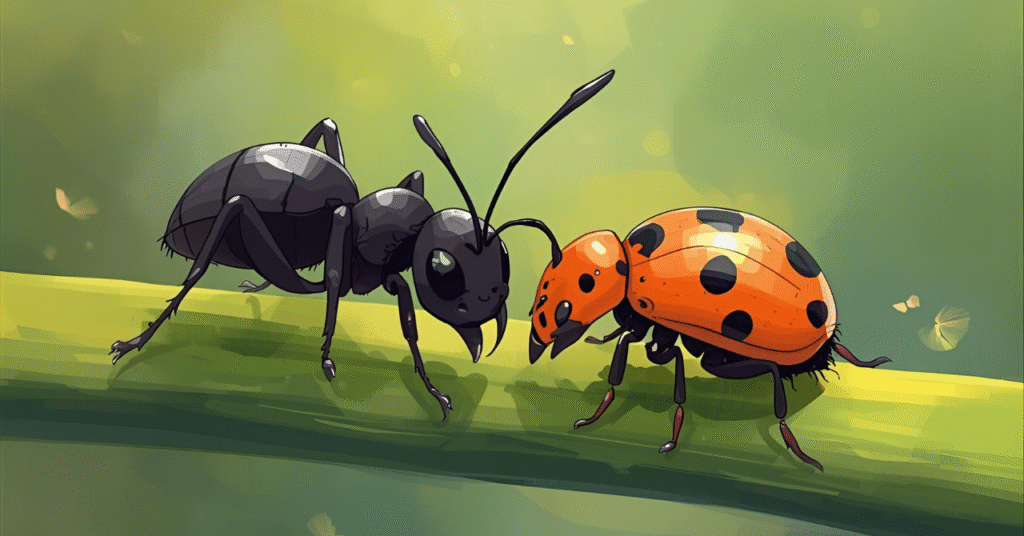
アリによるアブラムシの保護は、自然界では捕食者構造を変化させ、特定の植物群落における養分循環に影響を与えます。農業的には、アリがアブラムシを助けることでアブラムシ被害が増幅し得るため、アリ対策が防除戦略の一部になります。具体的には、アリの通路遮断や巣を標的にした制御(忌避剤・巣内処理など)を組み合わせることで、間接的にアブラムシ被害を軽減できる研究報告が複数あります。とはいえ、アリ自体が他の害虫を抑える役割を持つ場合もあり、単純に「アリは悪」とは言えません。局所の生態系を踏まえた総合的な管理が重要です
5. マイナーで面白い事例(観察して楽しい「小話」)
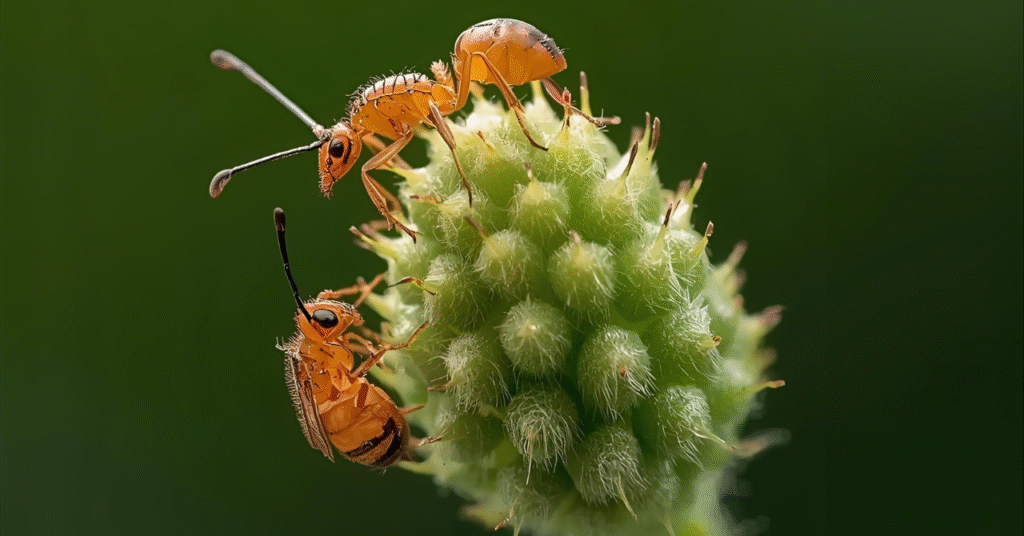
- 根アブラムシの『地下牧場』:ヨーロッパのLasius属などは巣の周囲に根アブラムシを養い、巣内で直接ハニーデューを収穫する例があります(地下での「農業」)。
- 「連れて歩く」アリ:一部のアリは、幼虫や卵の段階のアブラムシをつまんで植物上の最適位置に移す観察報告があります。歴史的にも1920年代から報告されてきた行動で、行動生態学の名物エピソードです。
- アリによる病害管理:アリは死んだ個体や感染個体を除去することで、集団内の病害伝播を抑える働きをすることが示されています。こうした“衛生行動”は家畜の群れ管理に似た側面を持ちます。
6. 研究の最前線と今後の課題 — 進化から応用まで
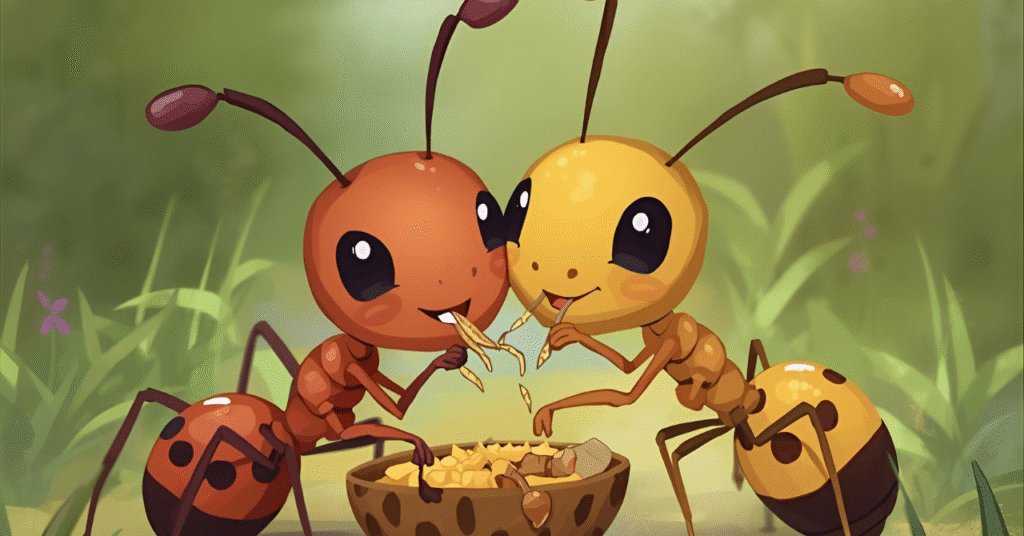
最近のレビューや研究は、アリ—アブラムシ共生がアブラムシの形態・行動・遺伝に与える進化的影響を明らかにしつつあります。例えば、アリに守られることで寄生蜂への感受性が変わり、それがアブラムシのライフヒストリーを変える可能性が示唆されています。また、ハニーデュー中の特定糖類がアリの嗜好を決め、結果的にアブラムシの代謝や行動が選択圧を受けるという“共進化”的な視点も注目されています。応用面では、農業被害軽減のために「アリ行動の操作」や「ハニーデューの質を変える」アプローチが実験的に検討されています。将来は、微生物(アブラムシ共生細菌)や植物との三者関係を介したより精密な制御法が登場するかもしれません。
まとめ(要点と実践的メモ)
- アリとアブラムシの関係は単なる「強盗と提供物」ではなく、相互利益に基づく高度に調整された共生(トロフォビオーシス)です。
- ハニーデューの糖組成(例:メレジトース)やアリの化学シグナルが関係の強さを決めます。
- 農業的には、アリ対策は効果的なアブラムシ管理手段の一つですが、地域の生態系全体を考慮した防除設計が必要です。
参考(抜粋)
- Ivens ABF et al., Aphid-farming ants: Current Biology, 2022. Cell
- Nielsen C. et al., Ants defend aphids against lethal disease, 2009. PMC
- Fischer MK et al., Host plant and ants influence the honeydew sugar composition of aphids, 2001. BES Journals
- Oliver TH et al., Ant semiochemicals limit apterous aphid dispersal, 2007. PMC
- Depa Ł. Ant‐induced evolutionary patterns in aphids, 2020. Wiley Online Library



