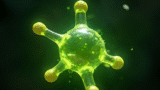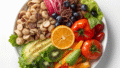はじめ
ケトーシス(ketosis)は、体が主なエネルギー源を糖(グルコース)から脂肪由来のケトン体へ切り替える生理的状態を指します。断食、炭水化物制限(ケトジェニック食)、長時間運動、またはインスリン低下などで起きます。単なる「ダイエットのトレンド」と捉えられがちですが、細胞レベルでは代謝経路・シグナル伝達・遺伝子発現が複合的に変化する複雑な現象です。本稿では、生物学的視点を重視して、分子メカニズムから臓器間連携、細胞内シグナル、医療・実験上の示唆まで、6つの主要トピック(+まとめ)に分けて詳しく解説します。

モアイ研究所
ケトン体に関するまとめ記事はこちら!ケトン体のみならず、関連する遺伝子などの様々な内容を統合しています!
1. ケトーシスとは何か(概念と特徴)

- 定義:血中の主要ケトン体(β-ヒドロキシ酪酸:BHB、アセト酢酸:AcAc、および呼気中のアセトン)が上昇し、組織がこれらを主要燃料として利用する状態。
- 発生条件:空腹・断食、低炭水化物食、長時間有酸素運動、インスリン欠乏(糖尿病性ケトアシドーシスは病的)など。
- 生理的意義:グルコース不足時に脳や筋肉へ迅速かつインスリン非依存的にエネルギーを供給する仕組みであり、飢餓耐性を高めます。
2. 「糖から脂肪へ」— 細胞が切り替えるトリガー(ホルモンとセンサー)

主なスイッチ要素:
- インスリン低下 / グルカゴン上昇
- インスリンが低下すると、ホルモン感受性リパーゼ(HSL)が活性化され、脂肪組織から遊離脂肪酸(FFA)が放出されます。
- 高遊離脂肪酸(FFA)濃度
- 肝細胞に取り込まれ、ミトコンドリアでβ酸化されアセチルCoAが増加。Acetyl-CoAの過剰がケトン合成を駆動します。
- 細胞内エネルギーセンサー(AMPK、mTOR、SIRT)
- ATP/AMP比の変化でAMPKが活性化すると脂肪酸酸化が促進され、mTOR抑制やSIRT活性が代謝再プログラミングを仲介します。
- 転写因子(PPARαなど)
- PPARαは脂肪酸酸化とケトジェネシス遺伝子を誘導します。これにより長期的な適応が成立します。
ポイントを簡潔にまとめると:
- ホルモン(インスリン/グルカゴン)→ リパーゼ活性 → FFA増加 → 肝でβ酸化→ アセチルCoA増 → ケトン生成、という流れです。
3. 肝臓でのケトン生成(ケトジェネシス)の分子ステップ(詳細)
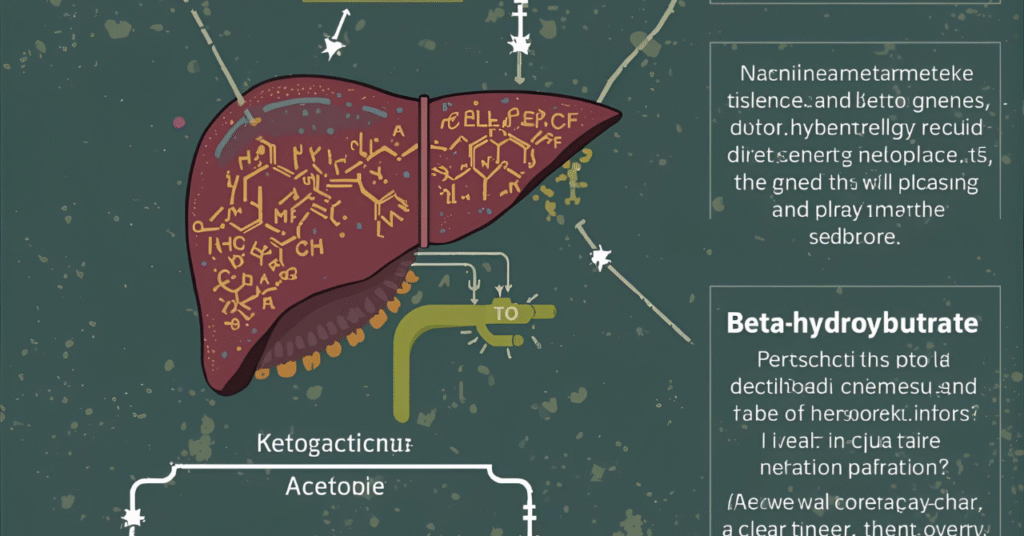
肝ミトコンドリア内での主な流れ:
- 脂肪組織からのFFA取り込み → 肝ミトコンドリアでβ酸化される。
- アセチルCoAの蓄積 → クエン酸回路(TCA)で消化しきれない場合、アセチルCoAはケトン体合成へ向かう。
- ケトン合成経路の主要酵素(例:HMG-CoAシンターゼ2:mitochondrial HMGCS2が律速酵素)を介して、アセチルCoA → HMG-CoA → アセト酢酸 → BHB 等へ変換される。
- 肝外組織へ放出:生成されたAcAc・BHBは血中へ放出され、末梢組織(脳、筋肉、心臓など)でケトン体輸送体(MCT:モノカルボキシレートトランスポーター)を介して取り込まれ、再びアセチルCoAに変換されTCA回路で酸化されます。
実験的に注目すべき点(マイナー情報):
- HMGCS2の発現は転写制御(PPARαやFoxa2など)で調整され、エピジェネティック修飾も報告されています。
- 肝内でのミトコンドリア膜電位やNAD+/NADH比が、ケトン生成速度に影響を与えるため、ミトコンドリア健康は非常に重要です。
4. 周辺組織でのケトン利用(トランスポーターと代謝経路)
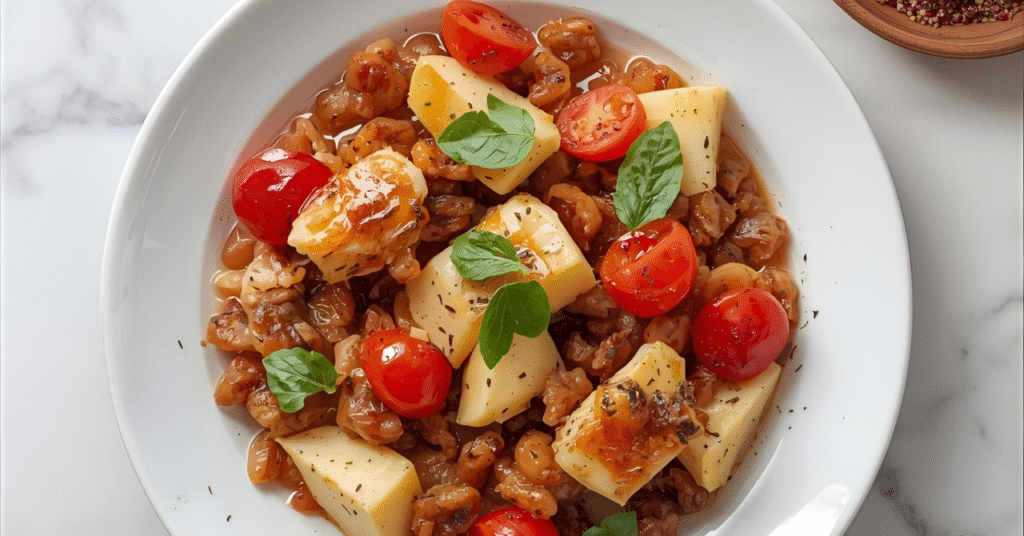
- 取り込み:BHBやAcAcはMCT1/MCT2などの輸送体を通じて細胞へ取り込まれます。取り込み後、BHBはBHBデヒドロゲナーゼでAcAcへ変換され、次にCoA付加を経てアセチルCoAへ戻されます。
- 脳における置換:飢餓が進むと脳は最大で必要エネルギーの約60〜70%をケトンで賄うとされ、これが筋タンパクの分解抑制に寄与します。
マイナーな実験観察:
- 筋や心臓ではMCTサブタイプの発現変化(運動や飢餓に伴う誘導)が報告され、局所的なケトン利用能の可塑性が示唆されています。
5. ケトン体は単なる燃料ではない — シグナル分子としての作用
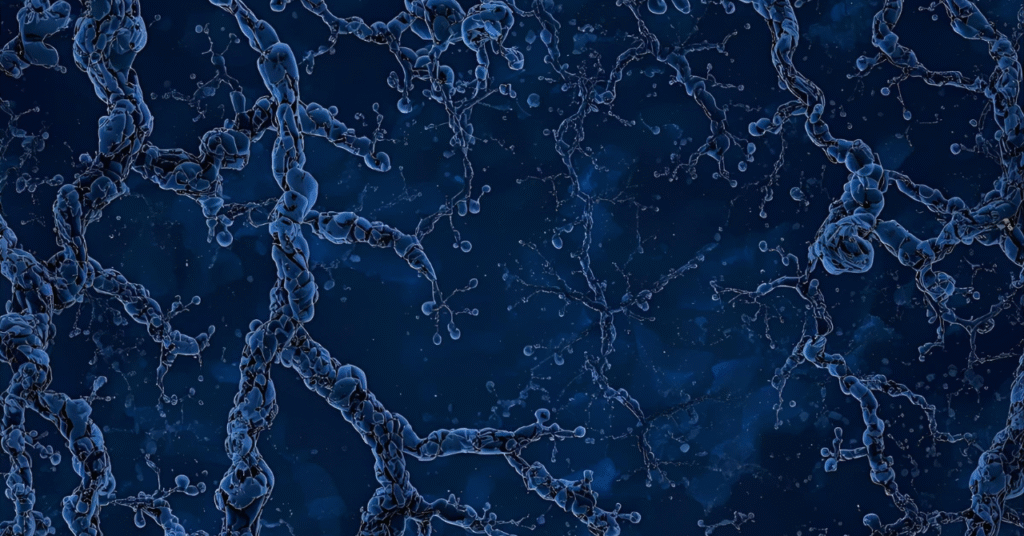
近年の研究で、ケトン体、特にBHBは代謝燃料以外のシグナル機能を持つことが明らかになっています:
- ヒストン修飾(ヒドロキシブチリル化):BHBはヒストンのリジン残基を修飾し、遺伝子発現を変える可能性があります(エピジェネティック効果)。
- HDAC(ヒストンデアセチラーゼ)の阻害:BHBがHDACを抑制し、抗酸化遺伝子やストレス応答遺伝子を誘導することで、保護的効果をもたらすという報告があります。
- 炎症抑制:NLRP3インフラマソーム抑制など、免疫調節的な作用も示唆されています。これらは神経保護や心血管代謝に関する臨床的関心を高めています。
研究的・臨床的インプリケーション
- 神経変性疾患・てんかん治療への応用(ケトジェニック食の古典的適応)。
- 心血管や代謝疾患におけるケトンの代謝・シグナル効果の治療ポテンシャル。
6. 実験的視点と注意点(ラボでの観察・測定法)

研究や臨床研究でよく使われる評価法:
- 血中BHB測定(血中/尿/呼気):短時間のケトーシス評価に便利。
- 遺伝子発現解析:HMGCS2、PPARα、CPT1などのmRNA変動をチェック。
- ミトコンドリア機能検査:酸化的リン酸化、NAD+/NADH比、呼吸制御比(RCR)など。
- 同位体トレーサー:脂肪酸からケトンへのフラックス解析には重水素や^13Cトレーサーが有用。
- 注意点:糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)と生理的ケトーシスを混同しないこと。DKAは高血糖+高ケトン+アシドーシスを伴う病的状態です。
マイナーな技術的留意点:
- 肝臓特異的にHMGCS2ノックダウンや過剰発現を行うと、全身のケトン分布とエピジェネティック・シグナルに与える影響を分離して解析できます。
- ケトン体の測定では、AcAcは不安定で測定誤差が出やすいため、BHBの定量が安定的指標となる場合が多いです。
まとめと今後の展望(臨床・研究の観点から)
- 要点の復習:ホルモン変動(低インスリン/高グルカゴン)→ FFA放出→ 肝でのβ酸化→ HMGCS2を介したケトン生成→ 末梢でのケトン利用、という一連の流れが「糖から脂肪へ」のスイッチを物理的に実現しています。
- 生物学的な重要性:ケトン体は単なる代替燃料にとどまらず、ゲノム制御、炎症応答、細胞ストレス応答に影響を与えるシグナル分子としての側面を持ちます。
- 今後の研究課題:
- 個体差(遺伝的背景・腸内微生物叢・ミトコンドリア機能)がケトーシス応答に与える影響の解明。
- ケトン体によるエピジェネティック制御のターゲット遺伝子の網羅的同定。
- 臨床応用に向けた安全性評価(特に慢性ケトジェニック食の長期影響)。
参考リンク
- Puchalska, P. & Crawford, P. A., Multi-dimensional Roles of Ketone Bodies in Fuel Metabolism and Signaling(Cell Metabolism, 2017)。
- StatPearls — Biochemistry, Ketogenesis(概説:ケトン生成の生化学)。
- Cahill GF Jr., Fuel metabolism in starvation(人の飢餓応答の古典的レビュー)。
- Laffel L., Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application(総説、1999)。
- Kolb et al., Ketone bodies: from enemy to friend and guardian angel(BMC Medicine, 2021)。