はじめ
セントラルドグマは、生命の設計図であるDNAの情報がどのようにしてRNAを経てタンパク質に変換されるかを説明する基本概念です。
簡単に言えば「DNA → RNA → タンパク質」と覚えられますが、実際には複雑な調節や例外も存在します。
この記事では、初心者でも理解でき、研究や日常の科学リテラシーにも役立つ内容を、6つのテーマに分けて解説します。
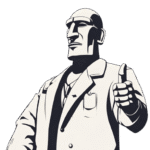
モアイ研究所
たんぱく質は体内で様々な役割を果たしています。詳細を知りたい方はこちら!
① セントラルドグマとは?
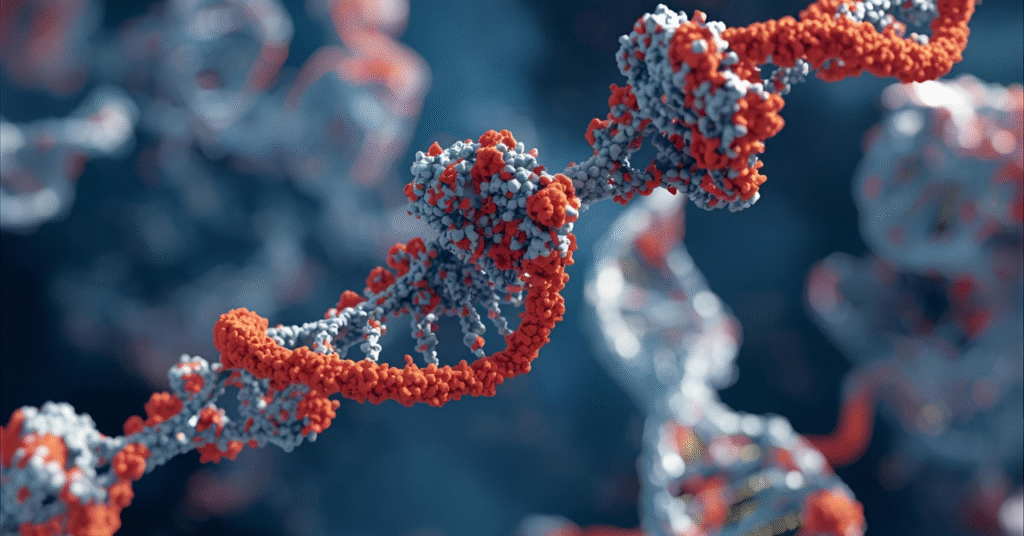
基本の流れ
- DNA(遺伝情報) → RNA(メッセンジャー) → タンパク質(機能分子)
誤解しやすいポイント
- タンパク質が直接DNAを書き換えることは通常ない
- 現代生物学では例外(逆転写やRNA編集)があるが、基本概念としては有効
ポイント
- 遺伝情報の流れを理解することは、基礎生物学・分子生物学の第一歩
- 後の転写・翻訳・応用技術の理解につながる
② 転写:DNAからRNAへ

転写の流れ
- DNAの特定部位(プロモーター)に転写因子が結合
- RNAポリメラーゼがDNAを読み取り、RNAを合成
- 前駆体mRNA(プレ-mRNA)が生成される
真核生物でのRNA成熟
- 5’キャップ:RNAを安定化させ、翻訳を助ける
- スプライシング:不要なイントロンを除去し、必要なエクソンを結合
- ポリアデニル化(poly-A尾):RNAの安定性を高める
ポイント
- 遺伝子1つから複数のタンパク質が生まれることもある(選択的スプライシング)
- 転写制御がタンパク質の量を左右する
③ 翻訳:RNAからタンパク質へ
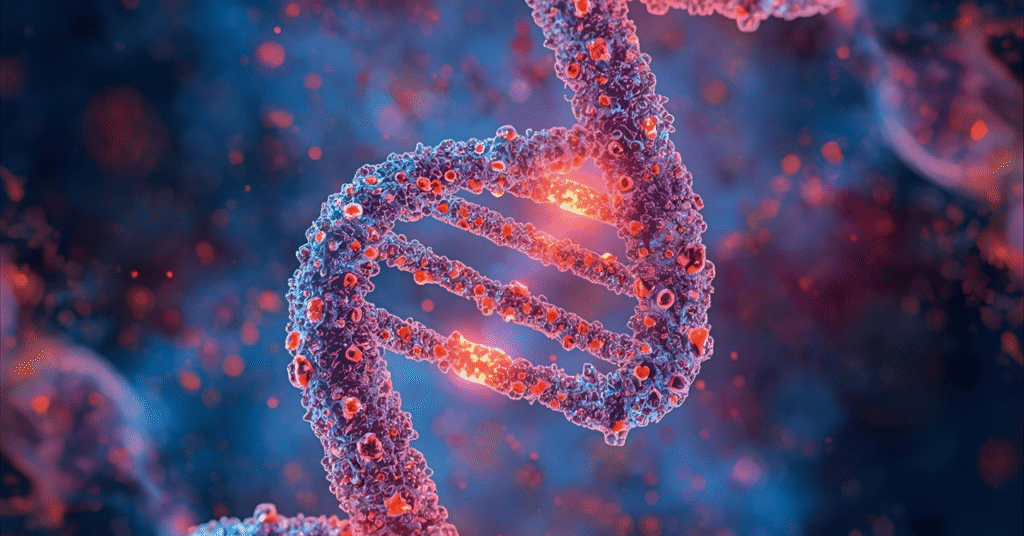
翻訳の流れ
- 開始:開始コドン(AUG)にリボソームが結合
- 伸長:tRNAがコドンを読み取り、アミノ酸を結合
- 終結:終止コドンでポリペプチドが完成
重要ポイント
- 読み枠がずれると全く別のタンパク質になる(フレームシフト)
- 翻訳後修飾でタンパク質の機能や安定性が調整される(リン酸化、グリコシル化など)
④ 例外・拡張:知っておきたいマイナーな現象
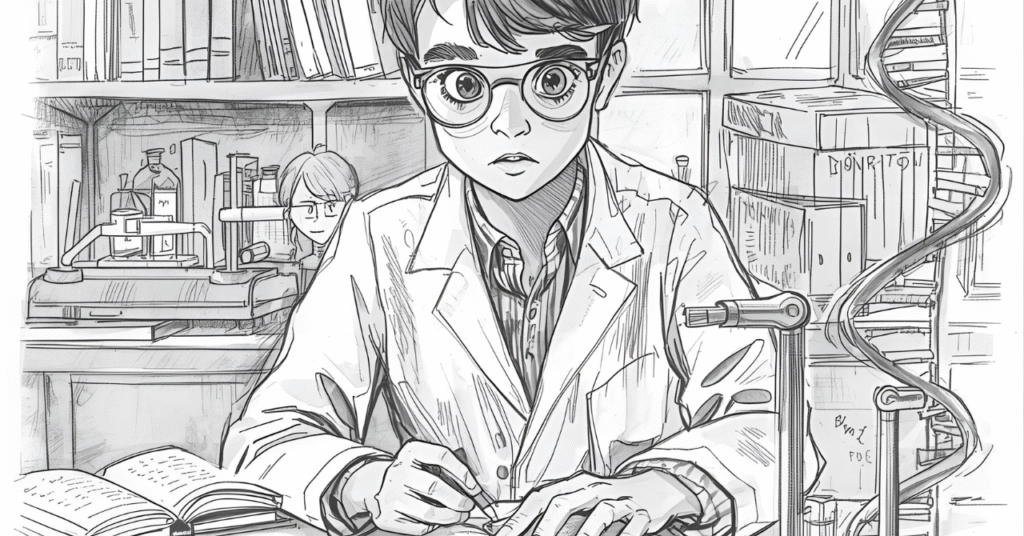
逆転写
- RNAを鋳型にDNAを作る現象
- レトロウイルスやテロメラーゼで見られる
RNA編集・化学修飾
- mRNAの塩基を化学的に書き換えることがある
- 安定性や翻訳効率に影響
非翻訳RNA(ncRNA)
- miRNAやlncRNAはタンパク質に変換されず、遺伝子発現を制御
プリオンや特殊翻訳
- タンパク質の形で情報が伝わる例(プリオン)
- フレームシフトやセレンシステイン挿入など、例外的ルールも存在

モアイ研究所
たんぱく質の摂取は大切なんですが、サプリメントの味が苦手な方がいるのも事実です。私は朝食などにこのようなたんぱく質多めな食事を心がけています。普段の食事に取り入れるだけで、簡単ですよ!
リンク
リンク
リンク
⑤ 実験・応用例
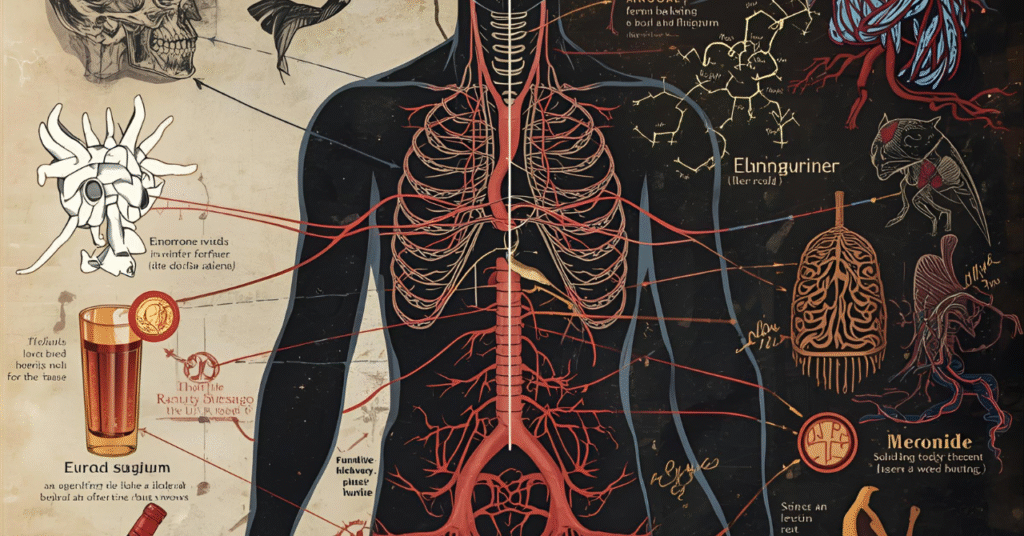
研究や医療での活用
- RT-PCR / RNA-seq:遺伝子発現やスプライシングの解析
- リボソームプロファイリング:翻訳の状態を解析
- mRNAワクチン:mRNAを体内で翻訳させ、免疫を獲得
- RNAi / アンチセンスオリゴ:特定mRNAを抑制して病気を治療
ポイント
- RNAの取り扱いは注意が必要(RNase対策)
- 例外現象を調べる場合はlong-read RNA-seqなど先端技術を活用
⑥ まとめ:理解のチェックリスト
- DNA→RNA→タンパク質の流れを説明できる
- 転写・翻訳で重要な酵素・因子を理解している
- mRNAの成熟過程(スプライシングなど)を理解している
- 逆転写・RNA編集・ncRNAなどの例外を知っている
- 主な解析技術(RT-PCR、RNA-seq)と利点・限界を把握
- 臨床応用(mRNAワクチン、RNAi)と関係性を理解
まとめ
セントラルドグマは一見単純ですが、実際には多くの調節や例外が存在します。転写・翻訳の基本を押さえつつ、例外的現象や応用技術を知ることで、分子生物学の理解がぐっと深まります。

モアイ研究所
私もランニングが趣味なのですが、長距離走をするにあたって、筋肉の維持は難しいんです。なのでプロテインをつかうことで、筋肉の材料を維持するように心がけています。プロテインの選択基準は、おいしさと安さです!
・ULTORAプロテイン
→ 公式サイト ←・My protein
【Myprotein】・HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBプレミアムマッスル ボディアをお勧めしています!


