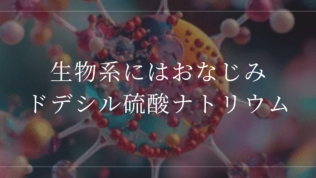栄養成分
栄養成分 【苦み、渋みといえばこれ】タンニンって何?徹底解説
タンニンは、自然界に広く存在する化学物質で、主に植物に含まれています。特に樹木や果物の皮、葉、種子に多く含まれており、渋味や苦味を与える成分としても知られています。タンニンは、植物が病気や害虫から身を守るために作り出す物質で、動物の消化を妨げることで、食害を防ぐ役割も果たします。タンニンには大きく分けて2種類あります。ひとつは「水溶性タンニン」で、もうひとつは「不溶性タンニン」です。水溶性タンニンは水に溶けるため、例えばお茶やワインの渋みを感じさせる要因となります。一方、不溶性タンニンは植物の細胞壁に結びついており、主に木材や果物の種子に多く見られます。