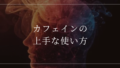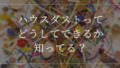はじめ
庭やベランダで「害虫は何とかしたい」──そんな方に向けて、**化学農薬に頼らずに害虫を抑える“庭で呼びたい益虫(とその関連天敵)を6種類”**に絞って、科学的な根拠と実践的な誘引方法を解説します。
この記事は科学系ブログの読者を意識し、各生物の捕食様式や生活史のポイント、誘引のコツ、現場での注意点(よくある誤解や落とし穴)も含めてできるだけ詳細にまとめています。読みやすさのために箇条書きや図式的な説明も取り入れていますので、実践にすぐ使っていただけます。
なぜ「益虫(natural enemies)」が効くのか — 科学的背景の要点

- 機能応答(functional response):捕食者は被食者(害虫)の密度に応じて捕食率が変わるため、ある程度の害虫発生を自然の天敵群が抑えることが期待できます。
- 生存率と世代交代:益虫の多くは複数世代で増えることができ、継続的な抑制効果を生みます(例:寄生バチやてんとう虫)。
- 群間相互作用の影響:アリがアブラムシを守るなど、益虫の働きを妨げる相互作用もあります。したがって「益虫を呼ぶ」だけでなく、周辺の生物相も管理する必要があります。
庭で育てたい益虫(+関連生物)6選 — 特徴・何を食べるか・誘引法

以下は「家庭の庭やベランダで比較的役立ちやすい(かつ誘引が現実的)」な6種です。各項目に「科学的なポイント」と「すぐできる誘引アクション」を示します。
1)テントウムシ(てんとう虫:Coccinellidae) — アブラムシの第一線
- 何を食べるか:アブラムシ、ハダニ類、うどんこ害虫の幼虫などの軟体小虫。成虫・幼虫とも捕食する。
- 科学的ポイント:1匹のてんとう虫は生涯を通じ数千匹のアブラムシを捕食するという報告があり、家庭菜園でのアブラムシ抑制に有効です。
- 誘引法(すぐできる):花蜜や花粉が得られる花壇(セリ科やシソ科など)を作る。冬季の越冬場所(落ち葉や木片)を残す。市販のてんとう虫を放す際は薬剤残留のない環境で、夕方に放すと定着しやすいです。
2)ヒラタアブ(ハナアブ;Syrphidae/hoverflies) — 幼虫がアブラムシハンター
- 何を食べるか:幼虫がアブラムシを好んで捕食。成虫は花蜜・花粉を摂取し、授粉も担う。
- 科学的ポイント:ハナアブの幼虫は発育期間中に数百匹のアブラムシを捕食することがあり、発生密度が高ければ局所的にアブラムシを大幅に減らす効果が報告されています。
- 誘引法:成虫が訪れる花を植える(小花を多数つける植物が好まれる)。アブラムシのいる場所にあえて近接して産卵する習性を利用し、無理に駆除せず「初期」段階でハナアブを呼び込むと効果的です。
3)クサカゲロウ(グリーンレースウィング;Chrysopidae) — “アブラムシのライオン”
- 何を食べるか:幼虫(“aphid lions”)がアブラムシ、スリップス、ハダニ、小さな卵類を捕食。
- 科学的ポイント:クサカゲロウ幼虫は一般的に貪欲な捕食者で、単一個体で多数のアブラムシを捕食可能とするデータがあります。生態系回復における汎用的天敵として温室・農地で広く利用されています。
- 誘引法:夜間に活動することが多いため、夜でも花蜜が取れる植物を混植する。農薬散布は禁忌。葉の裏や茂みを残して幼虫の隠れ場を作る。
4)寄生バチ(Aphidiusなど) — “内部寄生”でアブラムシを石化(ミイラ化)
- 何を食べるか(正確には寄生):アブラムシ類に卵を産みつけ、幼虫が内部で成長して宿主を死に至らせる(宿主は“ミイラ”化する)。
- 科学的ポイント:Aphidius属の寄生バチは多くのアブラムシ種に対して高い探索能を持ち、商業的にも生物的防除として利用されています。アリによる妨害を受けやすいため、周辺のアリ防除も重要です。
- 誘引法:花蜜を供給するインセクタリープランツ(誘引植物)を植える、アリをコントロールする、園芸上の広域な残薬を避ける(寄生バチは薬剤に弱い)。
5)エントモパソジェン(微生物的天敵:Beauveria、有益線虫Steinernemaなど) — 目に見えない“生物農薬”
- 何をするか:
- Beauveria bassiana(糸状菌)は接触感染で害虫の体表に付着→発芽→体内侵入→殺虫する。
- 有益線虫(Steinernema spp.など)は土中の害虫幼虫に侵入し、内肢内で致死させる。
- 科学的ポイント:これらは農・園芸で実用化されている生物的防除資材で、対象害虫や環境条件により効果は変動しますが、化学薬剤に比べヒト・動物への安全性が高く、IPM(統合防除)で重要な役割を果たします。
- 導入法:製品として市販されているため、対象害虫・使用時期・温湿度条件を確認して導入する。土壌処理型(線虫)や葉面散布型(Beauveria)など用途に合わせる。
6)コウモリ(夜間の空中捕食者) — 夜行性害虫(蚊・ガ)対策の強力な補助
- 何を食べるか:夜間に活動する小さな飛翔昆虫(蚊、蛾、ハエなど)。
- 科学的ポイント:種による違いはありますが、個体あるいはコロニー単位で大量の小型昆虫を捕食することが報告されています。夜間の蚊対策に対して有用な自然天敵となり得ます(ただし、コウモリだけで全数抑制するのは現実的でないことも指摘されています)。
- 誘引法:夜間でも安全に過ごせる隠れ場所(木の洞、コウモリ用ボックス)を設置する。街中の設置は地域ルールや衛生面も確認してください。
益虫を呼ぶ「実践的ガイド」:すぐできる6つの施策

- 花の連続開花(春〜秋)を確保する:花蜜・花粉があると成虫が集まりやすい。セリ科(ニンジン、フェンネル)やマメ科、キク科の小花を混植するのが有効です。
- 被害初期での“温存”:小規模のアブラムシ群落を見つけたら即殺さず、まず天敵を誘引して反応を見る。
- 広域殺虫剤・粒剤は極力使わない:広域効く薬剤は益虫も殺します。局所的な物理除去や低影響処置を優先します。
- アリ対策:アリがアブラムシを守ると寄生バチや捕食者の効果が激減します。アリの通り道を遮断する/誘引餌で管理する。
- 構造物を残す:落ち葉、枯れ茎、石の隙間は越冬や隠れ場になります。冬季に全部掃除するのは逆効果になることがあります。
- 必要に応じて生物製剤を導入:土壌害虫が問題なら有益線虫、葉面害虫ならBeauveriaなどの商用製剤を検討する(使用条件を厳守)。
実践上の注意点・よくある誤解(Q&A式で簡潔に)
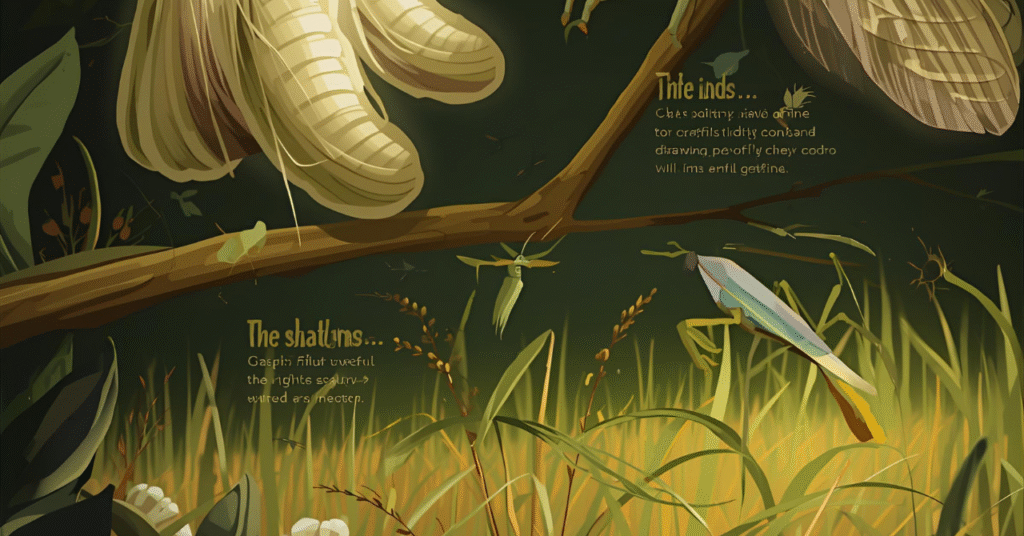
- Q:市販の益虫を放せばすぐに害虫が消える?
A:一時的な効果は期待できますが、定着と長期抑制には“餌(害虫)と越冬場所、薬剤回避”が必要です。 - Q:益虫は益だけ?副作用は?
A:捕食者は雑食性のものもあり、目的の害虫以外(ときに他の益虫)も捕ることがあります。カマキリなどは“総合的有益性”の判断が必要です。 - Q:コウモリの導入で蚊が完全に消える?
A:早期研究ではコウモリが多数の小型昆虫を食べる報告がありますが、地域によって効果は異なり“コウモリだけで完全抑制”は期待しすぎです。
まとめ(実践チェックリスト付き)
結論:池が作れなくても、庭やベランダで「益虫を呼ぶ設計」をすることで、化学薬剤に頼らない害虫管理は十分に可能です。特にテントウムシ、ヒラタアブ、クサカゲロウ、寄生バチ、微生物的天敵(Beauveria・有益線虫)、そして夜間の捕食者(コウモリ)は、それぞれ補完し合う形で害虫を抑えます。
すぐできるチェックリスト(今日から始められること)
- 花の小さな群落を1箇所作る(蜜源)
- 枯れ枝や落ち葉を少量残す(越冬場)
- 広域殺虫剤は使わない(まずは見守る)
- アリの通り道を点検・対策する(寄生バチ保護)
- 必要なら専門の生物製剤を検討する(対象・条件を確認)
参考
- https://ucanr.edu/blogs/real-dirt/article/ladybugs-are-good-your-garden
- https://cals.cornell.edu/integrated-pest-management/outreach-education/fact-sheets/hover-fly-biocontrol-fact-sheet
- https://cals.cornell.edu/integrated-pest-management/outreach-education/fact-sheets/common-green-lacewing-biocontrol-agent-factsheet
- https://ipm.ucanr.edu/natural-enemies/aphid-aphidius-parasitoids/
- https://cals.cornell.edu/integrated-pest-management/outreach-education/fact-sheets/beauveria-bassiana
- https://cals.cornell.edu/integrated-pest-management/outreach-education/fact-sheets/steinernema-carpocapsae-beneficial-nematode-sc
- https://batcon.org/wp-content/uploads/2020/04/calculate_the_value_of_bats_episode1.pdf