はじめに
オーストラリアの象徴的な有袋類、コアラ。彼らはユーカリを食べ、木の上でうたた寝をする可愛らしい姿で広く親しまれています。しかし最近、遺伝的多様性 (genetic diversity) の観点からコアラの将来に大きな不安があることが明らかになってきました。2024年、シドニー大学などの研究チームが「コアラ全体の遺伝マップ (ゲノムマップ)」を発表。これによって、特に危機にさらされている個体群とその原因が浮き彫りになっています。
本記事では、この発見の背景、科学的意義、保全への示唆、そして今後の展望を詳しく解説します。動物生物学、保全生物学、遺伝学に関心がある方にとって非常にホットなテーマです。
1. 背景:なぜ「コアラの遺伝的多様性」が今問題となっているのか

- ブラックサマー山火事 (2019–2020年):この期間、オーストラリアでは大規模な森林火災が起き、多くのコアラの生息地が燃えました。これが、単なる個体数の激減だけでなく、遺伝子レベルでの影響をもたらすリスクとして懸念されていました。
- 都市化・生息地断片化:道路建設、住宅地拡大などにより、コアラの生息地が細分化され、個体群間の移動が制限されるようになっています。これにより遺伝子の流れ (遺伝的混合) が阻まれ、近親交配 (inbreeding) のリスクが増大しています。
- ゲノム研究の未整備:火災後、どの個体群がどの程度遺伝的に打撃を受けたのか、正確なデータが不足していました。これを解消するために、遺伝子研究者らが大規模なゲノム調査 (Koala Genome Survey) を進めてきました。
2. コアラ全体のゲノムマップとは何か?— 2024年の重要な研究成果

- 研究チームとプロジェクト
- シドニー大学の Australasian Wildlife Genomics Group (生態・生命科学部) が中心となり、東部オーストラリア全域のコアラ個体群からサンプリングを実施。
- 参加はオーストラリア政府 (連邦・ニューサウスウェールズ州) の協力も得て、「Koala Genome Survey」という公開データリソースを構築。
- ゲノム解析の方法
- 数百匹以上のコアラから遺伝子サンプル (血液など) を収集し、ゲノム (DNA 全体) の遺伝多様性を解析。
- 特に「ホモ接合領域 (runs of homozygosity)」という指標を使って、近親交配の可能性や遺伝的多様性の低下傾向を評価。
- 主な結果
- ゲノムマップ上で、遺伝的多様性が特に低い地域が明確に見つかった。ニュージーサウスウェールズ (NSW) の沿岸部、ビクトリア州の一部など。
- Queensland (クイーンズランド) のコアラ個体群は相対的に多様性が高く、重要な遺伝的拠点であることが確認された。
- 一部の地域 (特に遺伝的に狭い個体群) では 高インブリーディング (近親交配) の兆候が見られる。
3. 科学的意義:なぜこの発見が重要なのか

- 適応力の減少リスク
- 遺伝的多様性が低い個体群は、将来の環境変化 (新しい病気、気候の急変など) に対する適応能力が弱くなる可能性があります。
- 絶滅リスクの増大
- 遺伝的に孤立した小さな個体群は、遺伝的浮動や近親交配による問題 (適応性の喪失、健康問題) を抱えやすくなります。これは保全生物学 (Conservation Genetics) において重大な懸念です。
- 保全戦略の精緻化
- ゲノムマップを使えば、どのコアラ個体群が「遺伝的に脆弱」かが明確になります。これにより、保護を優先すべき地域や個体群、野生放流・移動 (遺伝子交流) の必要性を具体的に検討できるようになります。
- 将来のリスク予測
- 将来的な気候変動や火災リスクを踏まえて、遺伝子多様性を維持するための管理プラン (コリドー設計、生息地保全) を設計する際に、ゲノムデータが強力な基盤となります。
4. 実際の保全への影響と課題
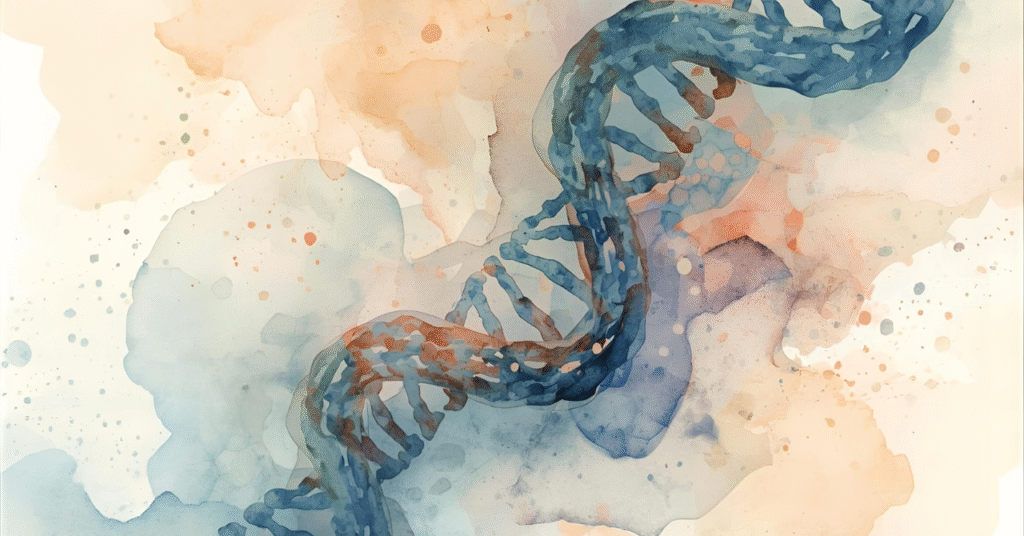
- 住民・都市との共存
- 遺伝的に脆弱なコアラ個体群は、都市化が進んだ地域 (道路、住宅地) と密接に関係しています。遺伝子マップによって、どの地域で人と共存しながら保護すべきかを考える指針が得られます。
- 野生間の遺伝子交流 (コネクティビティ)
- 分断された生息地をつなぐ“野生コリドー (動物回廊)”の整備が、遺伝子多様性を維持するために重要。ゲノムマップの情報を基に、最適なコリドー設計が可能になります。
- 再導入・移動戦略
- 将来的には、遺伝的に多様性の高いコアラを、遺伝的に危険な地域 (多様性が低く近親交配が進んでいる場所) に導入・移動させることで “遺伝的救済 (genetic rescue)” の可能性があります。ただし、移動によるストレスや病気伝播のリスクも慎重に評価する必要があります。
- モニタリング
- 遺伝子の変化を長期的に追跡 (モニタリング) する体制が必要。ゲノムマップを定期的に更新して、保全活動の効果を評価します。
5. 今後の展望:守るべきコアラの未来をどう設計するか

- さらなるサンプリング
- 現時点のゲノムマップは非常に価値あるものですが、まだ未調査地域 (小さな孤立集団) がある可能性。将来的にはより広範な採取と解析が望まれます。
- 遺伝子駆動型保全プラン
- ゲノムデータを活用して、「遺伝的ホットスポット (多様性が高い地域)」や「遺伝的ボトルネック (多様性が危険な地点)」を戦略的に管理。
- 地域ごとの保護優先度の再設定
- 全体保護だけではなく、遺伝的観点から “特に遺伝的にもろさのある地域” を重点保全。
- 市民参加型モニタリング
- 地元住民、ボランティア、自然保護団体が携わり、コアラの遺伝子モニタリング (例えば採尿・採糞サンプル) や生息地保全活動を支える。
- 教育・広報
- ゲノム保全の重要性を一般市民にも理解してもらう。コアラが「かわいいだけの動物」でなく、遺伝学や生態学の重要なモデルであることを発信。
6. おわりに
コアラはその可愛らしさで世界中から愛されていますが、その遺伝的な健康状態は決して楽観できるものではありません。2024年に発表された ゲノムマップ は、特定地域のコアラが遺伝的に脆弱である可能性を示し、今後の保全活動の方向性を大きく左右する成果です。
私たちがコアラを守るためには、個体数の回復だけでなく、「遺伝子の多様性をどう保つか」を考える必要があります。ゲノム情報を活かした戦略的な保全は、気候変動や将来の災害に強いコアラ集団を育てるための鍵です。
科学として、保全として、未来への投資として――ゲノムマップを活かす行動を今始めることが、コアラの長期的な生存を支える大きな一歩になります。
参考文献
- McLennan, E., Hogg, C., et al. (2024). Genomics identifies koala populations at risk across eastern Australia. 本研究ではゲノムマップによって遺伝多様性の地域差と高い近交係数が明らかになった。
- Australasian Wildlife Genomics Group, University of Sydney (2024). New map shows where koalas are at most risk. シドニー大学によるニュース発表。
- Fabijan, J., University of Adelaide (2020). Understanding the true impact of bushfires on our Koala population. カンガルー島のコアラ調査を通じた火災後の個体群分析。
- Dunstan, E., Funnell, O., McLelland, J., et al. (2021). “An Analysis of Demographic and Triage Assessment Findings in Bushfire-Affected Koalas … on Kangaroo Island, South Australia, 2019–2020.” Animals, 11(11), 3237. 火災による個体の救助・リハビリ状況を記述。
- Conservation Genetics (2025). “Low genetic diversity and high inbreeding in one of the last chlamydia-free strongholds for New South Wales koalas.” 遺伝多様性と近交の定量評価。
- WWF (2024). Impacts of the unprecedented 2019–20 bushfires on Australian animals. 火災が哺乳類 (コアラを含む) に与えた影響を総合的に報告。


