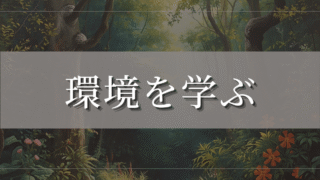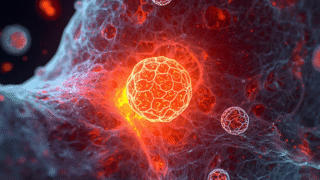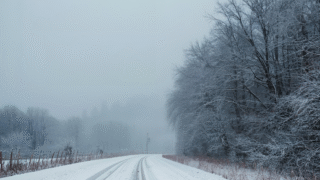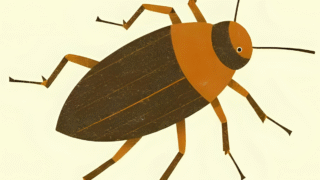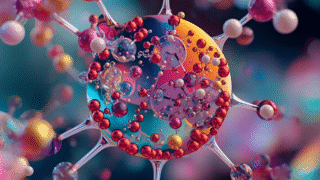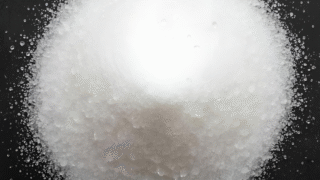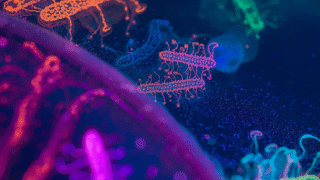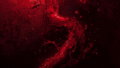食品添加物は日々の食生活に密接に結びついています。添加物という言葉を聞くと「体に悪い」「できるだけ避けたい」と感じる方が多いですが、そもそも添加物とは何で、どのような基準で使われ、どんなリスクと利益があるのかを科学的に整理することで、冷静に判断できるようになります。この記事では、食品添加物の定義や規制の仕組みをわかりやすく説明した上で、**注目すべき10種類(用途別)**について、研究や規制の最新事情を交えて解説します。
1. 食品添加物とは?:定義と基本ルール

食品添加物は「通常それ自体を食品として消費しない物質で、製造・加工・保存・包装などの目的で意図的に食品に使用され、その結果として食品の成分や特性に影響を与えるもの」と定義されています(国際的な基準であるコーデックスの定義に準拠)。つまり、添加物は「食品を安全に、安定に、そして食べやすくするための技術的役割」を持っています。
食品添加物は用途や化学的性質により、保存料、着色料、甘味料、乳化剤、pH調整剤、酸化防止剤などに分類されます。重要なのは「有害無害の白黒だけで判断できない」点で、用量(摂取量)と exposure(暴露)に基づくリスク評価が必須だという点です。
2. 規制と評価の仕組み(国際基準と日本の制度)

食品添加物は各国で厳しい評価プロセスを経て許可されます。国際的にはコーデックス・アルティタリウス(Codex)が基準を示し、各国の規制機関(欧州のEFSA、米国のFDA、国連機関のJECFAなど)がデータをもとに安全性評価を行います。欧州では評価結果により使用禁止や制限が決まることがあります(例:酸化性や遺伝子毒性の懸念で食品への使用が問題視された物質)。
日本では厚生労働省が指定添加物や既存添加物、公定書などを通じてリスト管理と基準設定を行っています。また、消費者が分かるように表示ルールも定められており、加工食品には原則として使用した添加物名の表示が義務付けられています。最新の法令やリストは厚生労働省の公式ページで公開されています。
3. 注目の10選(用途別に短評)

以下は「注目して読んでおきたい添加物10種(またはカテゴリー)」です。科学的論点と現時点での規制動向、消費者が実践できるポイントを簡潔に示します。
- 亜硝酸塩(亜硝酸ナトリウム) — 保存料/発色剤
- ハム・ソーセージなどで使われる。発色と殺菌効果がある一方、調理や消化過程でニトロソ化合物が生成される可能性があり、過剰摂取は注意。加工肉とがんリスクの関連はIARC等でも議論されているため、摂取頻度を下げるのが現実的対策です。
- 人工甘味料(アスパルテーム等) — 甘味料
- カロリーゼロの利点がある一方、IARCによる「possibly carcinogenic(2B)」分類や、JECFA / EFSA のADI(許容一日摂取量)評価の違いが注目されています。過剰摂取は避けるべきで、特に子どもや妊婦の習慣的摂取には配慮が必要です。
- 二酸化チタン(TiO₂、E171) — 着色料(白色)
- 以前は菓子や加工食品の白色化に広く使われてきましたが、EFSAの評価で遺伝子毒性の懸念が示され、EUでは食品への使用が事実上禁止となっています。現在も各国で評価が続いており、製品表示の確認が推奨されます。
- 保存料(ソルビン酸、安息香酸など)
- 微生物の増殖抑制に有効で食の安全に寄与。通常の摂取量では問題ないとされていますが、アレルギー反応や過敏症の報告もあり、個人差を考慮する必要があります。
- 乳化剤・増粘剤(カルボキシメチルセルロース、カラギーナンなど)
- 食感改良に重要ですが、近年「腸内細菌叢への影響」や炎症促進に関する動物・臨床研究が増えています。ランダム化給餌試験やin vitro研究で悪影響が示された例もあり、研究は進行中です。頻繁に摂る加工食品を減らすことが対策になります。
- 酸化防止剤(BHA/BHT、アスコルビン酸等)
- 油脂の酸化防止や風味保持に有効。BHA/BHTは動物実験での懸念が過去に議論されましたが、各機関が用量ベースのリスク評価を行っています。
- 着色料(合成着色料:赤色○号など)
- 視覚的魅力を高める反面、過敏症や行動への影響(特定の子どもにおける多動傾向の可能性)が研究されています。欧州では食品に着色料の使用に注意喚起がある例もあります。
- 香料(天然/合成)
- 多くは低濃度で使用され安全性が確認されていますが、複合的な化学物質の混合暴露(ミックス効果)に関する研究は不十分な点があります。アレルギー既往がある場合は表示を確認。
- 酸味料・pH調整剤(クエン酸等)
- 基本的に安全性が高く、微生物制御にも貢献します。過度の酸性食品は歯のエナメルに影響するため、摂り方に注意。
- ナノ材料(添加物ではないが関連問題)
- E171等のように粒子サイズ(ナノ領域)の特性が体内挙動に影響する可能性があり、今後の評価テーマです。
4. 科学が示す「リスク」と「誤解」——よくある問いに答える

Q1. 「合成=悪、天然=安全」は本当ですか?
A. いいえ。天然由来でも毒性を示す物質は多く、合成でも低リスクなものは多いです。大切なのは用量(dose)と暴露の累積です。表示を見る習慣を持ち、どれくらいの頻度で何を食べるかで判断してください。
Q2. 「無添加」表示は安全の証拠ですか?
A. 「無添加」はマーケティング用語として使われることが多く、必ずしも安全性の保証ではありません。日本の表示制度では原料や用途によって「無添加」の表現に制限があるため、裏面表示(原材料名)を確認するのが確実です。
Q3. 少量なら問題ないの?
A. 「少量なら問題ない」は基本原則で、規制はそれを前提にしています。ただし長期的な低用量暴露や混合物の相互作用に関する科学は未解明な部分もあるため、過度な常習摂取は避けるべきです。
5. 日常ですぐできる“安全に付き合う”3つの方法

- 加工食品の頻度を減らす:加工度の低い食品(生鮮、簡易調理)を中心にすると、添加物暴露は自然に下がります。
- 表示を習慣化する:包装の原材料欄をざっとでも見る習慣をつけ、特定の添加物を避けたい場合はチェックする。日本では用途別表示や一覧が確認できます。
- 多様な食事でリスク分散:同じ加工食品を毎日摂ると特定添加物に偏る可能性があるため、食材や調理法を多様化することが有効です。
6. まとめ:何をどう選べばよいか(Q&A形式で要点整理)

- 添加物は“全て悪”ではない:食品の安全性・保存性・食味を支える重要な役割を持ちます。
- 問題になるのは“暴露量”と“長期的な累積”:規制は用量に基づきますが、研究が進む分野(腸内細菌影響、ナノ物質など)もあります。
- 個人でできる対策:加工食品を減らす、表示を確認する、食の多様化を図る、の3点をまず始めてください。
参考リンク(本文中にはリンクを貼っていません。詳細を確認したい場合はこちらを参照してください)
- WHO — Food additives (fact sheet).
- Codex Alimentarius — General Standard for Food Additives (CXS 192-1995).
- EFSA — Titanium dioxide (E171) safety opinion (2021) / EU action.
- EFSA — Aspartame topic page (ADI considerations).
- WHO / IARC & JECFA statements on aspartame (2023).
- FDA — How the FDA regulates food additives (overview).
- 厚生労働省 — 食品添加物 一覧・食品添加物公定書(日本の制度).
- PubMed / MicrobiomeJournal / Gastroenterology — 乳化剤・増粘剤(carboxymethylcellulose, carrageenan 等)の腸内細菌叢・臨床影響に関する研究(Chassaing, Naimi ら)。