ビタミンは生命維持に不可欠な微量栄養素ですが、単なる栄養補助にとどまらず、細胞レベルの代謝や遺伝子発現、さらには腸内微生物との相互作用まで幅広く関わります。現代の分子生物学研究では、各ビタミンがどの酵素やシグナル経路に結合し、どのように細胞機能を調節するかが明らかになってきています。本記事では、よく知られた作用だけでなく、あまり知られていない分子機構や最新の研究成果を紹介します。
1. ビタミンの分類と分子的特徴

ビタミンは脂溶性と水溶性に大別されます。
脂溶性ビタミン(A, D, E, K)
- ビタミンA(レチノール、レチナール、レチノイン酸)
- 作用機序:レチノイン酸は核内受容体RAR(Retinoic Acid Receptor)やRXR(Retinoid X Receptor)に結合し、転写因子として特定の遺伝子の発現を制御します。
- 生物学的機能:視覚(11-cis-レチナールがロドプシン形成)、皮膚・粘膜の分化、免疫応答調節。
- ビタミンD(コレカルシフェロール、カルシトリオール)
- 作用機序:カルシトリオール(活性型)はVDR(Vitamin D Receptor)に結合し、カルシウム輸送蛋白(カルバシンD、TRPV6)の発現を誘導。骨形成や免疫系、腸内細菌叢の調節に関与。
- 注目点:マクロファージでの抗菌ペプチド(カテリシジン)産生を促進。
- ビタミンE(α-トコフェロール)
- 作用機序:脂質過酸化反応のラジカル捕捉。細胞膜脂質の過酸化による損傷を抑制し、酸化ストレス応答を緩和。

モアイ研究所
ビタミンEをとりたいけどオリーブオイルって高価ですよね。コスパを考えると私はこちらが一番だと感じています!
リンク
- ビタミンK(フィロキノンK1、メナキノンK2)
- 作用機序:γ-カルボキシル化酵素の補酵素として、プロトロンビンやオステオカルシンなどのGlaタンパク質をカルボキシル化。血液凝固、骨代謝、動脈石灰化抑制に必須。

モアイ研究所
ビタミンKは発酵食品を摂取することで、腸内細菌が作ってくれます!ヨーグルトってどれもおいしいんですが、製品によって味わいや口当たりって全然違うんですよね。私はこちらのヨーグルトがねっとりとしており、お気に入りです!
リンク
リンク
水溶性ビタミン(B群、C)
- ビタミンB1(チアミン)
- 作用機序:チアミンピロリン酸(TPP)としてピルビン酸デヒドロゲナーゼやα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼの補酵素となり、糖代謝・エネルギー産生に必須。
- ビタミンB2(リボフラビン)
- 作用機序:フラビンモノヌクレオチド(FMN)やフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)として酸化還元酵素の補酵素。電子伝達系でATP産生を支える。
- ビタミンB6(ピリドキサールリン酸)
- 作用機序:アミノ酸代謝酵素(トランスアミナーゼ、デカルボキシラーゼ)の補酵素。神経伝達物質(セロトニン、GABA、ドーパミン)合成にも関与。
- ビタミンB12(コバラミン)
- 作用機序:メチルコバラミンはメチオニン合成酵素の補酵素。デオキシリボ核酸合成や神経機能維持に必須。
- ビタミンC(アスコルビン酸)
- 作用機序:水溶性抗酸化物質。プロリルおよびリシル水酸化酵素の補因子としてコラーゲン合成に必須。鉄の還元・吸収も促進。
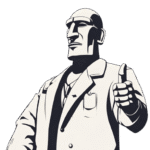
モアイ研究所
ビタミンCはサプリでも接種できますが、食品添加物用のものを買うと安く購入することができます。私は牛乳に入れてラッシーみたいにして飲んでます!溶かして飲むと体にも吸収しやすいです!
リンク
2. ビタミンと腸内細菌の分子相互作用
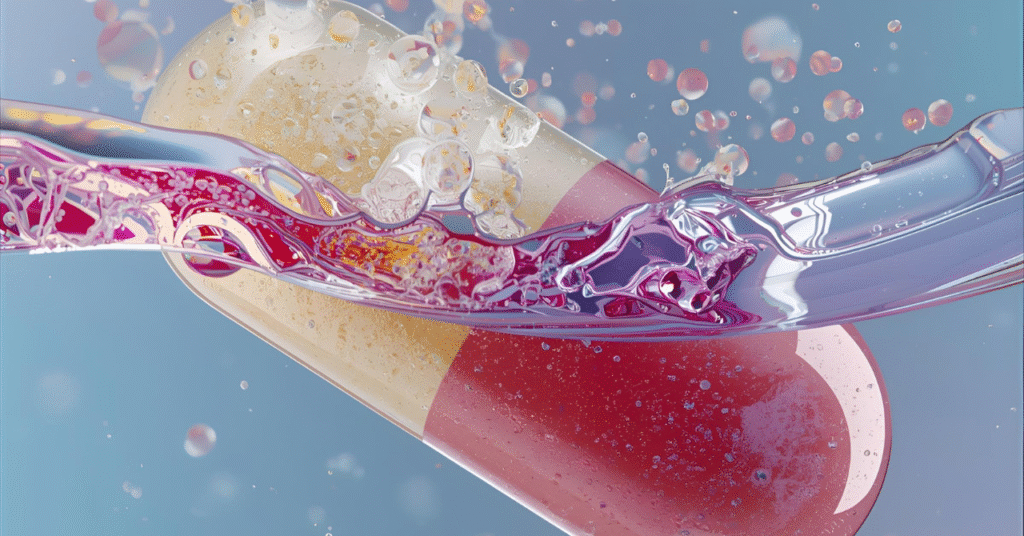
- 腸内細菌によるビタミン産生
- ビフィズス菌やラクトバチルスはB群ビタミン(B2, B9, B12)を産生。宿主はこれを吸収して代謝に利用。
- ビタミンによる腸内フローラ制御
- ビタミンDの活性型(カルシトリオール)はVDRを介して抗菌ペプチド(カテリシジン、β-ディフェンシン)の発現を誘導し、腸内微生物のバランスを制御。
- 相互作用の意義
- 腸内細菌とビタミンの双方向作用は、免疫調節や慢性炎症のリスク低下に関連。
3. マイナーだが重要なビタミンの作用機序

- ビタミンB5(パントテン酸)
- コエンザイムAの前駆体として脂質代謝・TCA回路に不可欠。副腎皮質ホルモン(コルチゾール)合成にも関与。
- ビタミンB7(ビオチン)
- ピルビン酸カルボキシラーゼ、アセチルCoAカルボキシラーゼの補酵素として、糖新生や脂肪酸合成を制御。ヒストンビオチン化によるエピジェネティック制御にも関与。
- ビタミンK2(メナキノン)
- ミトコンドリア電子伝達系に影響し、ATP産生や神経保護作用を補助することが最新研究で示唆されている。
4. ビタミン欠乏と分子レベルの影響

- B1欠乏:TPP不足によりピルビン酸デヒドロゲナーゼ活性低下、乳酸蓄積。神経障害(脚気)を引き起こす。
- B12欠乏:メチルコバラミン不足でメチオニン合成が障害され、DNA合成低下→巨赤芽球性貧血。
- ビタミンD不足:カルシウム輸送蛋白の発現低下で骨形成障害、免疫不全。
- ビタミンC不足:プロリル・リシル水酸化酵素が機能不全、コラーゲン形成障害→壊血病。
5. 最新研究と進化的視点

- 進化的制約
- 多くの哺乳類はビタミンCを体内合成可能だが、人間やサル科動物ではGULO遺伝子が不活化。食事からの摂取が必須。
- 医療応用
- ビタミンD補充による感染症予防や、ビタミンB群補充による神経疾患予防の臨床試験が進行中。
- パーソナライズ栄養学
- 遺伝子多型や腸内フローラに基づき、個人ごとに最適なビタミン摂取量を設計する研究が注目。
6. まとめ
ビタミンは単なる栄養素ではなく、酵素補因子、転写調節因子、抗酸化物質として、細胞レベルで多岐にわたる生物学的役割を果たしています。腸内微生物との相互作用や進化的視点を取り入れることで、これまで見過ごされてきた作用機序や健康への影響が明らかになっています。今後は、遺伝子や微生物叢の個人差を考慮した、より精密なビタミン研究が期待されます。
参考文献
- Gropper SS, Smith JL. Advanced Nutrition and Human Metabolism. 7th Edition. 2020.
- Blom HJ, Smulders YM. “Overview of homocysteine and folate metabolism.” European Journal of Pediatrics. 2011;170(2):177-185.
- O’Leary F, Samman S. “Vitamin B12 in health and disease.” Nutrients. 2010;2(3):299-316.
- Cantorna MT, Snyder L, Lin YD, Yang L. “Vitamin D and 1,25(OH)2D regulation of T cells.” Nutrients. 2015;7:3011-3021.
- LeBlanc JG, et al. “B vitamins production by lactic acid bacteria.” Microbial Cell Factories. 2011;10:34.









