はじめに
夏の夜に突然あらわれる大量のカメムシ、川や海で水が赤く染まる「赤潮」、公園の池にびっしりと広がるアオコ。こうした「生物の大量発生」は、ニュースで取り上げられることも多く、「なぜこんなに一気に増えるの?」と不思議に思ったことはありませんか?
実は、大量発生には いくつかの共通する原因 があり、自然界のバランスが崩れると一気に表面化します。本記事では、その原因を6つにまとめて、わかりやすく解説していきます。ちょっと専門的な内容も、身近な例やイメージを使って説明しますので安心してください。
1. 気温や天気の変化

- 暖かい冬 → 害虫が死なずに越冬
- 長い雨や日照不足 → 水の流れが悪くなり藻が増える
例えば、暖冬の年は害虫が寒さで死なずにたくさん残り、春になると一気に数が増えてしまいます。海では水温が上がると、特定の藻が増えやすい環境になり「赤潮」と呼ばれる現象が起きます。
気温や天気はコントロールできませんが、毎年の気候傾向を観察することで「今年は多いかも?」と予想することができます。
2. 栄養の増えすぎ(富栄養化)
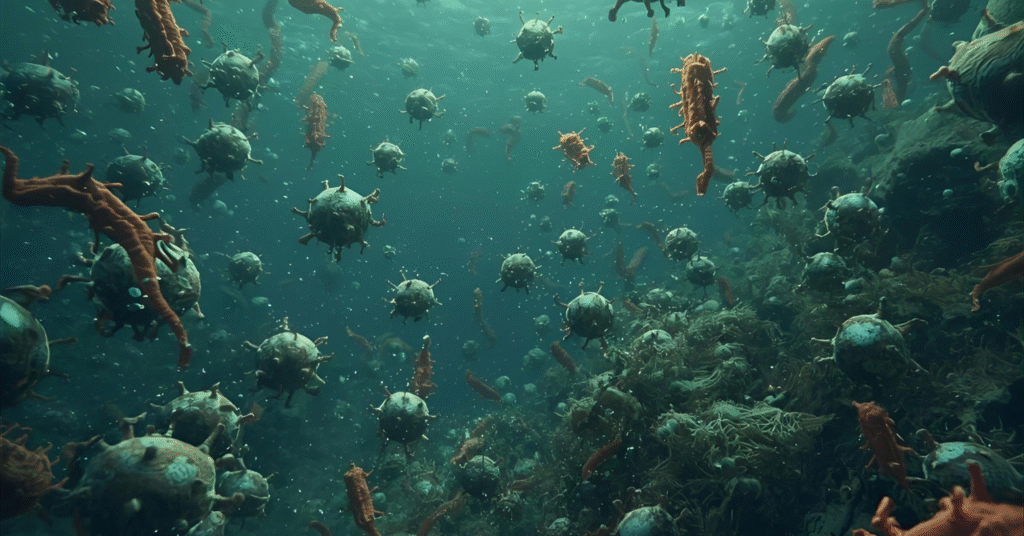
- 田んぼや畑からの肥料が川に流れこむ
- 下水や工場排水に含まれる栄養分が湖にたまる
栄養が多すぎると、藻や水草が急に増えます。人間でいえば「食べ放題でエネルギーが余る」ようなもので、微生物や藻がどんどん繁殖してしまいます。これが池や湖でのアオコの原因です。
解決策としては、肥料や排水を減らす工夫(農地の水路に草を植える、排水処理をしっかり行うなど)が有効です。
3. 天敵がいなくなる

自然界では「食べる側」と「食べられる側」のバランスがあります。
- テントウムシが少なくなるとアブラムシが大発生
- 魚が減るとプランクトンが増えすぎる
農薬をたくさん使いすぎたり、森林伐採で動物の住処がなくなったりすると、天敵が減ってしまいます。そうなると、本来なら増えすぎないはずの生物が一気に増えてしまうのです。
4. 外来種の侵入

海外から持ち込まれた生き物が、日本の自然で爆発的に増えることがあります。
- アメリカザリガニやウシガエル
- ヒアリなどの外来昆虫
外来種はもともとの生態系に「敵」がいないため、止めるものがなく、爆発的に数を増やしてしまうのです。
5. 化学物質や汚染
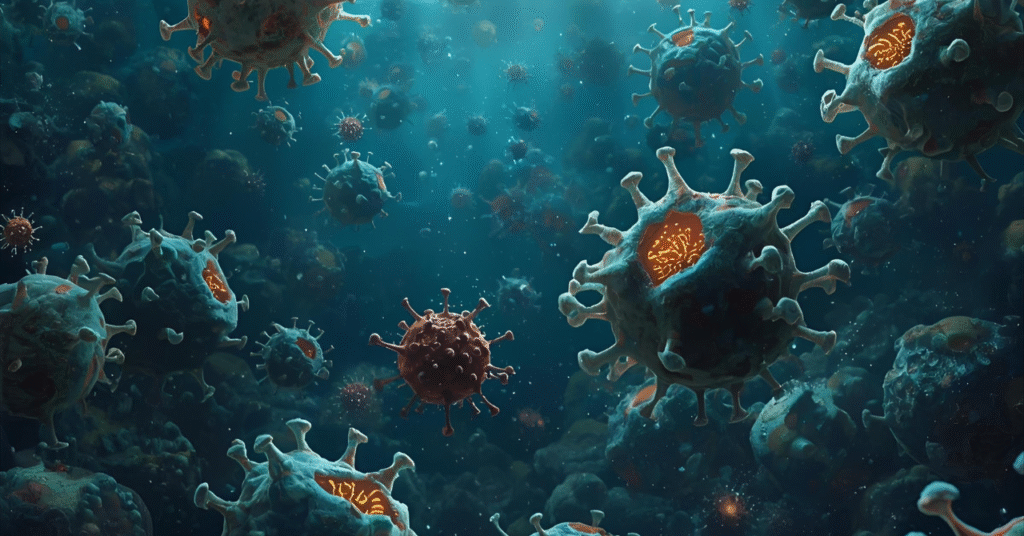
農薬や化学物質の影響で、生態系のバランスが変わり、特定の生物だけが増えることがあります。
- 農薬で天敵が死ぬ → 害虫が増える
- 汚染で一部の微生物が優先的に増える
少しマイナーな例ですが、化学物質が昆虫の「集まれ!」という信号(フェロモン)に影響して、普段よりも群れをつくりやすくなるケースも報告されています。
6. 微生物や細菌の「合図」
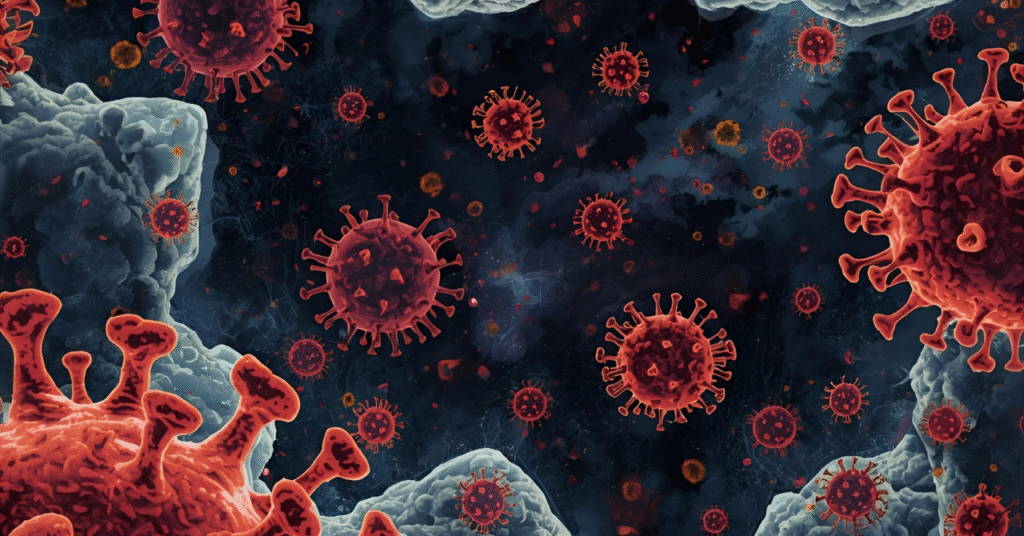
目に見えない小さな生き物も、大量発生の原因をつくります。
細菌は「仲間が増えたぞ!」とお互いに合図を出す仕組みを持っていて、一定数を超えると一気に増殖モードに切り替わります。これを「クオラムセンシング」と呼びます。
また、微生物を食べるウイルス(ファージ)の増減によっても、大量発生が抑えられたり、逆に爆発的に増えたりします。ちょっと専門的ですが、自然界では「目に見えないレベルの戦い」が大量発生を左右しているのです。
まとめ
生物の大量発生には、次の6つの原因が関係しています。
- 気温や天気の変化
- 栄養の増えすぎ(富栄養化)
- 天敵がいなくなる
- 外来種の侵入
- 化学物質や汚染
- 微生物や細菌の「合図」
つまり「自然界のバランスが崩れたとき」に起こりやすいのです。
大量発生は農業や漁業に大きな影響を与えますが、日常生活でも「蚊が多い夏」や「池が緑色になる現象」として私たちが実感するものです。普段から自然の変化に気をつけることで、大量発生の兆しをつかむことができるかもしれません。
参考リンク
- 環境省(日本) — https://www.env.go.jp/
- NOAA:What is a Harmful Algal Bloom? — https://www.noaa.gov/what-is-harmful-algal-bloom
- FAO:Locusts and other migratory pests — https://www.fao.org/locusts/en/
- 国立環境研究所(NIES, Japan) — https://www.nies.go.jp/


