はじめに
緊張したとき、ドキドキしたり、手が震えたりした経験はありませんか?
それは「アドレナリン」というホルモンが関係しています。
アドレナリン(英語:epinephrine)は、私たちの体が“危険”や“ストレス”を感じた瞬間に分泌される物質です。いわば「体を一瞬で戦闘モードに切り替えるスイッチ」です。
この記事では、
- アドレナリンがどこで作られるのか
- 体のどんな部分にどう作用するのか
- 医学や研究でどう利用されているのか
- そしてあまり知られていない進化的・研究的なお話
まで、生物学の視点でわかりやすく説明します。
読みやすさを重視し、箇条書きも交えていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. アドレナリンはどこで作られる?

アドレナリンは、腎臓のすぐ上にある「副腎(ふくじん)」という小さな臓器の中で作られます。
その中心部分「副腎髄質(ずいしつ)」には、“クロマフィン細胞”という特別な細胞があり、ここでチロシンというアミノ酸から何段階も反応して作られます。
作られる流れはこんな感じです👇
チロシン → ドーパ → ドーパミン → ノルアドレナリン → アドレナリン
作られたアドレナリンは小さな袋(小胞)にしまわれ、必要なときに一気に放出されます。
たとえば、
- 強いストレスを感じたとき
- 急にびっくりしたとき
- 体が危険を察知したとき
などに、神経の信号で一瞬にして血液中に放たれるのです。
放出された後は、肝臓などでMAO(モノアミン酸化酵素)やCOMTという酵素によって分解され、体外に排出されます。
つまり、アドレナリンは「出てはすぐ消える」短時間勝負のホルモンです。
2. アドレナリンの受け皿「受容体」とは?

アドレナリンは、全身のいろいろな細胞にある「受容体(レセプター)」に結合して働きます。
受容体のタイプによって効果が変わるのがポイントです。
主な種類と働きはこちら👇
| 受容体の種類 | 主な場所 | 主な働き |
|---|---|---|
| α1受容体 | 血管 | 血管をギュッと縮めて血圧を上げる |
| α2受容体 | 神経 | 神経の興奮を少し抑える |
| β1受容体 | 心臓 | 心拍数・心臓の力を上げる |
| β2受容体 | 肺・筋肉 | 気道を広げる、筋肉を動かしやすくする |
| β3受容体 | 脂肪組織 | 脂肪を分解してエネルギーを作る |
このように、アドレナリンは一つの物質なのに、結合する受容体の種類によって全く違う効果を出すのです。
だからこそ「全身が一気に活性化する」ような感覚になるのです。
3. アドレナリンの驚くべき作用6選!
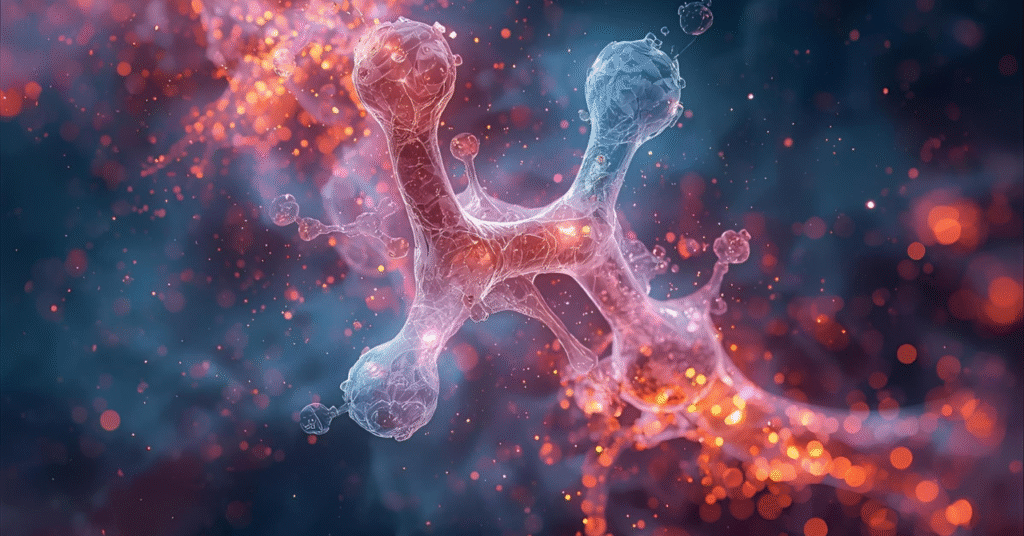
① 心拍数を上げて血を送る
ドキドキするのは心臓が速く、強く打つからです。
アドレナリンが心臓のβ1受容体に結合し、「もっと血を送れ!」という指令を出します。
② 血流を重要な部分へ集中させる
アドレナリンは手足や皮膚の血管を収縮させ、脳や筋肉に優先的に血液を送ります。
これにより、素早い判断や逃げる・戦う行動をサポートします。
③ 呼吸を楽にする
β2受容体を通じて気管支を広げ、酸素を多く取り込めるようにします。
喘息の治療薬に「アドレナリンの仲間」が使われるのはこのためです。
④ エネルギーを一気に供給する
肝臓ではグリコーゲンを分解して血糖を増やし、脂肪組織では脂肪を分解して燃料を作ります。
アドレナリンは“体の緊急バッテリー”のような働きをします。
⑤ 痛みや炎症を抑える
意外かもしれませんが、アドレナリンには痛みを感じにくくする作用もあります。
これは脳や免疫細胞にも受容体があるためで、「一時的に痛みを感じにくくする」ストレス応答の一部です。
⑥ 記憶力や集中力を高める
緊張した場面ほど覚えていることってありますよね。
アドレナリンは脳の「海馬」や「扁桃体」にも作用し、記憶を強化します。
この仕組みは“生き延びるための学習”として進化したと考えられています。
4. 医療や研究でのアドレナリン

アドレナリンは、救急医療の現場でも重要な薬として使われています。
- **アナフィラキシー(重度のアレルギー反応)**のときに注射する「エピペン」はアドレナリンです。
- **心停止時の救命処置(心肺蘇生法)**でも、血圧と心拍を回復させるために使われます。
- 局所麻酔薬に少し加えると、血管が収縮して薬が長く効くようになります。
また、研究の世界では血液や尿中のアドレナリンを**HPLC(高速液体クロマトグラフィー)**などで測定し、ストレス反応や代謝の研究にも使われています。
5. あまり知られていないアドレナリンの話

● 進化の中でも重要なホルモン
アドレナリンに似た物質は魚やカエルなどの脊椎動物にも存在します。
「危険を感じたら逃げる」という反応は、生物が共通して持っている生存戦略なのです。
● 遺伝子の違いで反応が変わる?
人によって「緊張しやすい」「動じにくい」などの性格差があります。
これは、アドレナリンを作る酵素や受容体の遺伝子の微妙な違い(多型)が関係している可能性があります。
● 新しい薬の開発にもつながる
近年の研究では、「受容体の中のどのシグナルを強く出すか」を選んで作動する“選択的アゴニスト”が注目されています。
つまり「良い効果だけ出して、副作用は少なくする」ような薬が開発されつつあります。
6. まとめ:アドレナリンは“体を守るためのスイッチ”
アドレナリンは、危機に直面したときに一瞬で体を動かすための強力なホルモンです。
まとめると👇
- 副腎で作られ、ストレスで一気に分泌される
- 受容体の種類によって多様な効果を出す
- 短時間で体の反応を最大化させる
- 医療や研究でも重要な役割を持つ
そして、最近の研究では「ストレスホルモン」としての側面だけでなく、記憶・免疫・代謝にも深く関わっていることが分かってきています。
アドレナリンは、まさに“生きる力を支える分子”なのです。
参考文献(検索用タイトル)
- 「Principles of Neural Science」Kandel et al.
- “Adrenergic receptors and catecholamines” Review Article
- “Epinephrine in human physiology and medicine”
- “Measurement of catecholamines in plasma and urine”
- “Biased agonism at GPCRs: a new direction in drug discovery”


