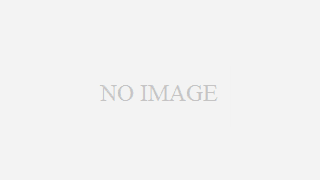 昆虫
昆虫 頭がなくても生きる?ゴキブリの驚異の「生存力」7つの科学的理由(生物学的に解説)
ゴキブリは「最強生物」として都市伝説的に語られることが多く、中でも「首を切っても生きる」「頭がなくても動き回る」といった話は非常に有名です。本記事ではその伝説を科学的に解きほぐし、ゴキブリの神経系・代謝・感覚・生理的適応を中心に、なぜ頭がなくても短時間なら生存できるのか、どの程度までの生命維持が可能かを詳しく説明します。専門用語は丁寧に解説し、研究のマイナーな発見や応用例も取り上げます。
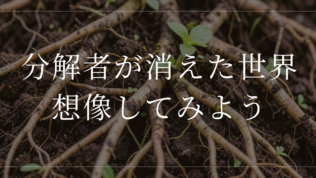 微生物
微生物