「体温=37℃」という数値はよく知られていますが、なぜその値が“標準”とされるのか、どれほど厳密な値なのか、そしてその背後にある生物学的な理由や進化的なトレードオフについては意外と知られていません。本記事では、科学的エビデンスをもとに「37℃がどのようにして最適になったか」をわかりやすく解説します。
1. 37℃という基準はどう決まったのか?(歴史とばらつき)
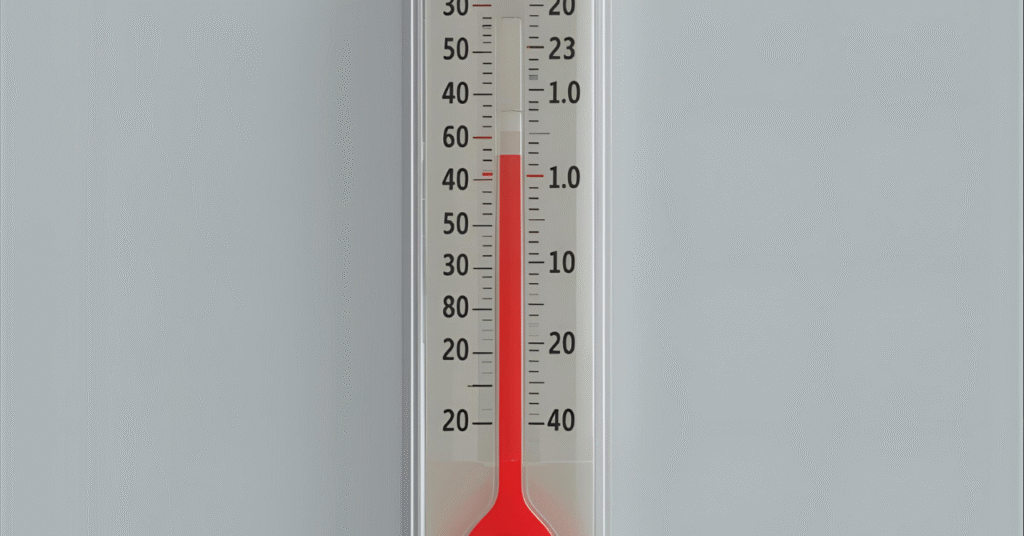
・「37℃(98.6°F)」という数値は19世紀のドイツの医学者が大量の測定から導いた平均値に由来します。しかし個人差・測定部位(口腔・腋下・鼓膜・直腸)・時間帯(概日リズム)で変動します。実際の「正常範囲」は約36.0–37.5℃と考えられています。
・日内変動:深夜〜早朝に低く、午後〜夕方にやや高くなる(約0.5℃程度の振幅)が一般的です。年齢やホルモン状態(女性の月経周期)でも変化します。
2. 体温を一定に保つ「恒常性(ホメオスタシス)」の仕組み
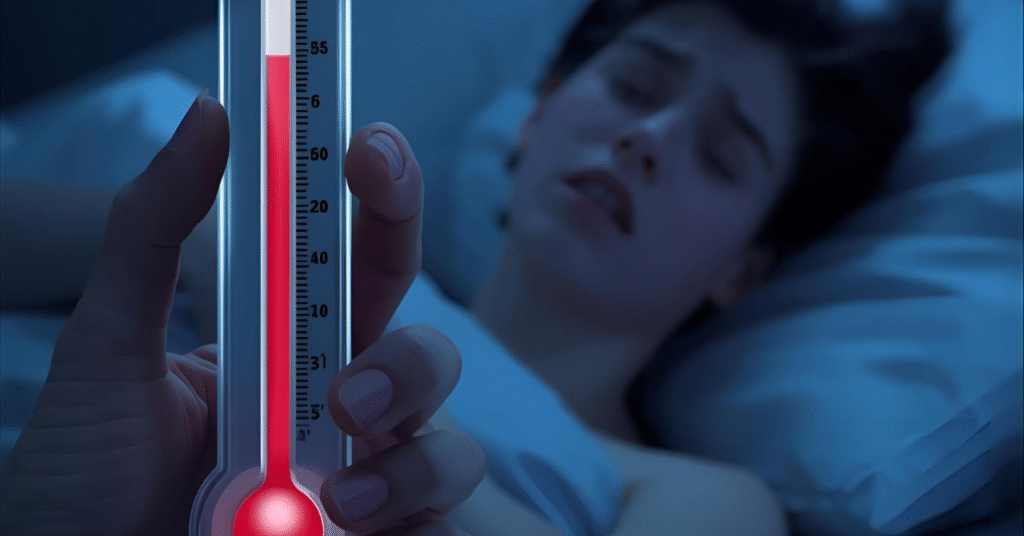
体温は「脳(視床下部)の設定値(セットポイント)」と、末梢の熱産生・放散のバランスで保たれます。主な要素は以下です。
主な調節機構(簡潔まとめ)
- 中枢のセットポイント:視床下部の特定神経群が体温の目標値を設定します。
- 熱産生:基礎代謝、筋収縮(震え)、褐色脂肪組織(特に新生児や寒冷時)による非震え性熱産生。
- 熱放散:皮膚血流の調節(血管収縮/拡張)、発汗、呼吸による放熱。
- 化学的メディエーター:プロスタグランジンE2(PGE2)などがセットポイントを上げ下げします(発熱時や解熱薬の作用点)。
臨床的には、発熱は「セットポイントの上昇」によるもので、寒気や震えは新たな高いセットポイントへ体を合わせるための反応です。解熱薬(アスピリンなど)はPGE2合成を阻害してセットポイントを下げます。
3. 37℃が「生存に有利」な理由:酵素・免疫・代謝の観点から
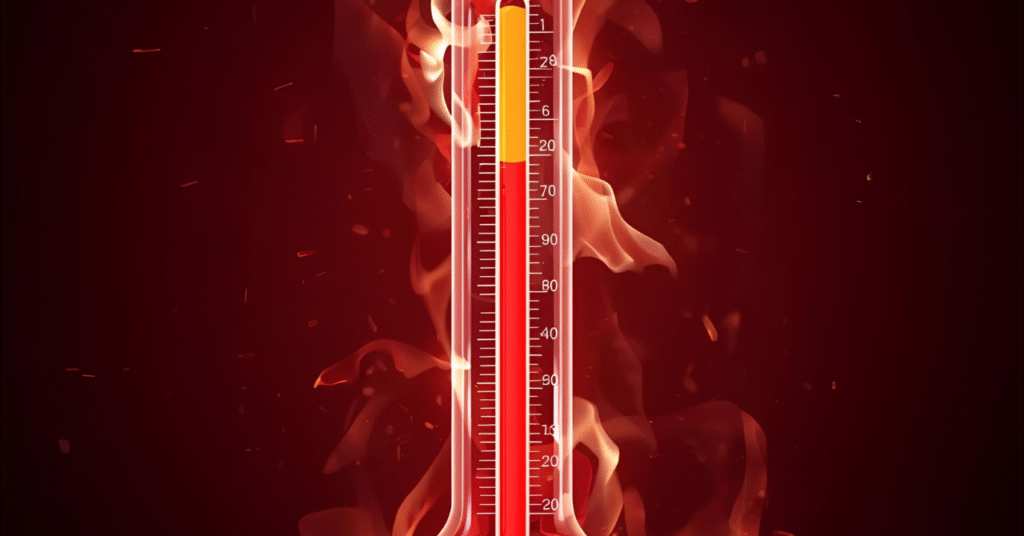
なぜ生物はこの温度を“選んだ”のか?主に次の4点が重要です。
- 酵素反応の最適化
酵素反応速度は温度に敏感で、多くのヒト酵素は37℃付近で最も効率良く働くよう進化しています。温度が上がると反応速度は上がりますが、一定を超えるとタンパク質変性(失活)で逆に機能が落ちます。酵素の熱力学的特性(ΔCp‡など)が最適温度を規定します。 - 免疫機能の最適化(発熱の意義)
発熱は単なる副作用ではなく、病原体増殖を抑えつつ免疫反応(白血球の貪食能、サイトカイン産生、抗原提示など)を高める適応的応答です。多くの研究が、発熱によって自然免疫および獲得免疫が効率化されることを示しています。 - 代謝効率とミトコンドリア機能
基礎代謝やATP生産の効率は温度に依存します。37℃付近は細胞内でのエネルギー変換が安定して進む温度帯です(極端な低温や高温は代謝障害を招きます)。一方で高温は酸化ストレスやタンパク質損傷を誘発します。 - 熱ストレス応答(ヒートショックタンパク質)
高温によりヒートショックタンパク質(Hsp)が誘導され、タンパク質折りたたみを助けますが、慢性的・過度の高温になると保護能を超えて損傷が蓄積します。したがって中間的な温度が最も“安全かつ効率的”なのです。
(まとめ)これらの要素がトレードオフとなり、酵素の活性・安定性、免疫効率、代謝の安全性を総合した“妥協点”として約37℃が機能的に有利だったと考えられます。
4. 37℃は「進化的トレードオフ」の産物である
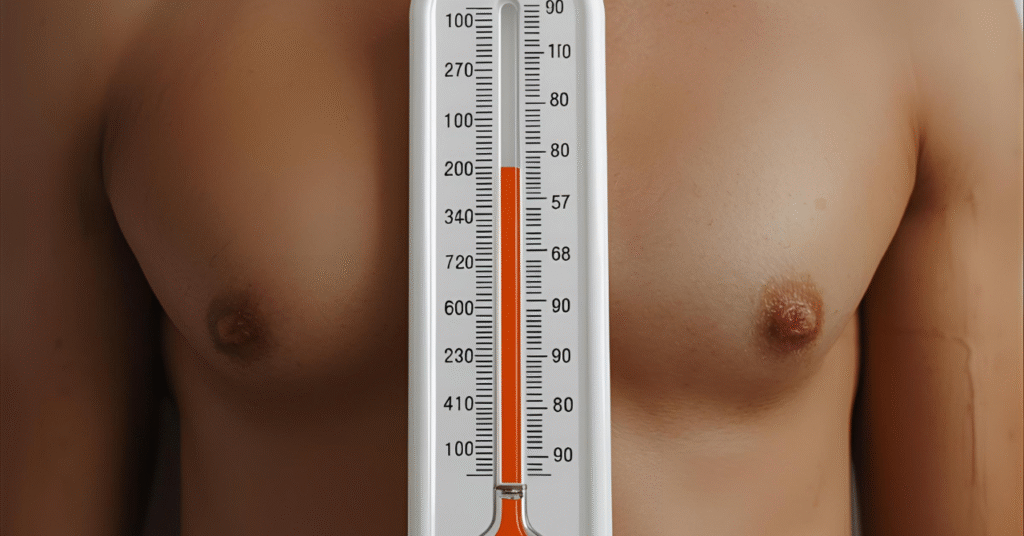
・「より高い温度で反応速度を上げれば良いのでは?」という疑問が出ますが、高温はタンパク質の不安定化、DNA損傷、膜流動性の変化をもたらします。一方、低温は代謝速度を落とし、病原体の一部は低温で好適に増殖するため必ずしも有利ではありません。
・さらに、外界の温度変動を受けにくい体温制御(恒温性)を持つことは、多様な環境で活動する能力を与え、行動的・生理的な利点をもたらしました。褐色脂肪や発汗などの仕組みは、その代償(エネルギー消費や水分損失)を負担してでも体温を守る価値があったことを示しています。
5. 例外と個人差:すべての生物が37℃ではない

・恒温動物でも種や年齢で最適体温は異なります(鳥類はやや高め、ネズミは高めなど)。爬虫類など変温動物は外界温度に体温が左右され、行動で温度を調節します(日向ぼっこなど)。
・ヒトでも新生児・高齢者・発熱感受性には差があり、特に新生児は褐色脂肪による熱産生が重要で、老年期は発熱反応が鈍ることが知られています。臨床では「同じ体温でも高齢者では感染のサインが見逃されやすい」点に注意が必要です。
6. 日常でできる体温管理とよくある誤解
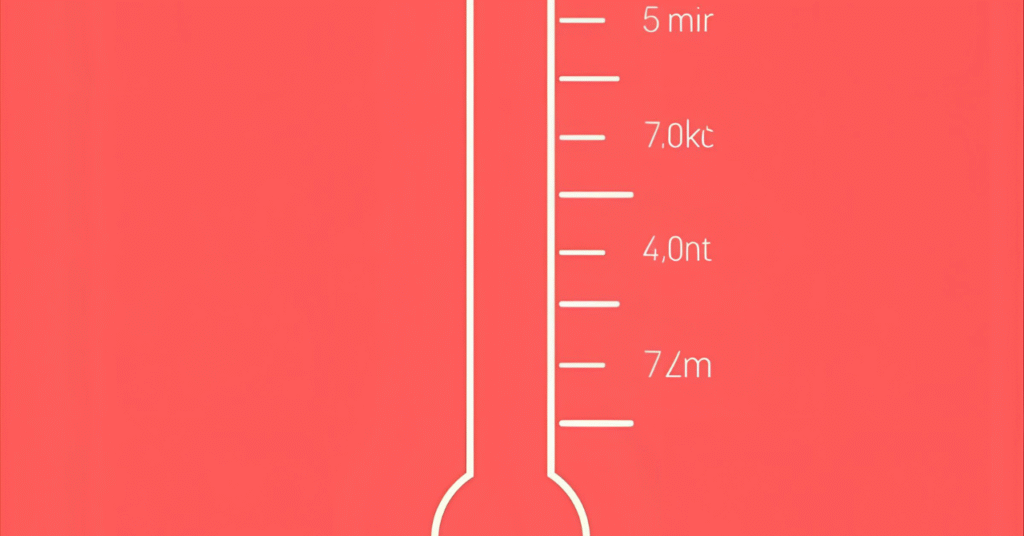
実践的なポイント
- 睡眠・食事・適度な運動は基礎代謝を整え、健康的な体温リズムを保ちます。
- 風邪や感染での「悪寒=必ずしも重症ではない」一方、高熱(例:40℃超)は注意が必要です。特にけいれんや意識障害がある場合は受診してください。
- 解熱薬は症状緩和に有効ですが、発熱の“生理的メリット”もあるため、全ての発熱で無条件に解熱するべきではありません(年齢・基礎疾患を考慮する)。
よくある誤解
- 「37℃を超えたら必ず病気」ではありません(個人差・運動後・午後は上がりやすい)。
- 「発熱=悪」ではなく、状況次第で防御機構である場合が多いです。しかし高熱は代謝負担であり、特に心疾患や脳血管障害のある人は注意が必要です。
まとめ:37℃は偶然ではなく“適応の産物”
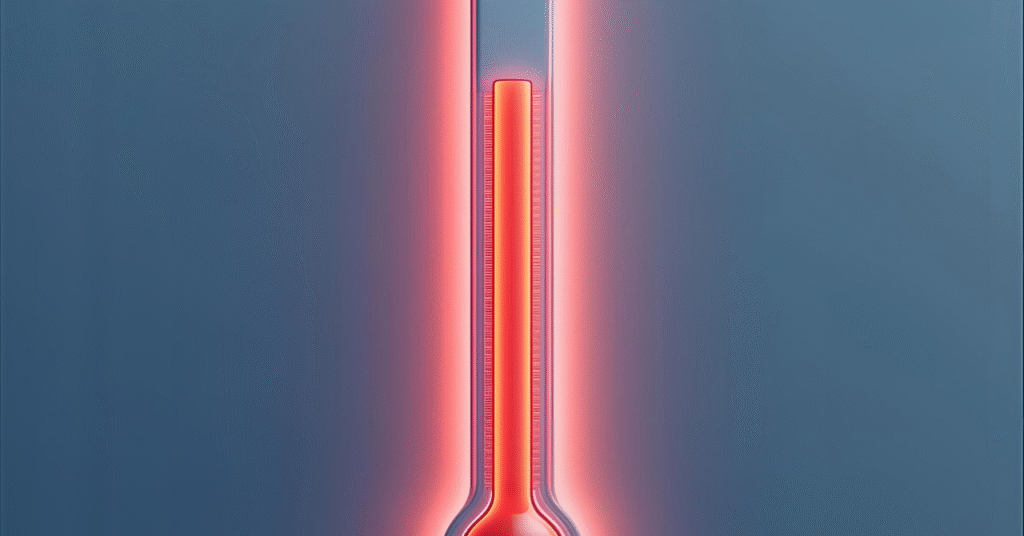
・37℃という値は歴史的経緯とともに、酵素活性、免疫効率、代謝の安定性、熱損傷の回避といった生物学的トレードオフを反映する“妥協点”です。発熱はこのバランスを一時的に書き換えて免疫を優位にし、複雑なメカニズム(PGE2経路など)を通じて制御されます。
最後に(読みやすさのための要点まとめ)
- 正常体温は「37℃を中心とした幅(約36–37.5℃)」です。
- 視床下部とPGE2が体温のセットポイントを制御します。
- 発熱は免疫を助ける適応的反応であり、状況に応じて解熱の是非を判断します。
参考
- StatPearls — Physiology, Temperature Regulation. (NCBI Bookshelf).
- StatPearls — Physiology, Fever. (NCBI Bookshelf).
- Evans SS, et al., “Fever and the thermal regulation of immunity” (Nat Rev Immunol / PMC review).
- Arcus VL, “On the Temperature Dependence of Enzyme-Catalyzed Rates” (Biochemistry).
- Bienboire-Frosini C., et al., “The Role of Brown Adipose Tissue and Energy Metabolism in Humans” (2023 review).
- CCForum — “The pathophysiological basis and consequences of fever” (2016).


