はじめに
「爬虫類に気持ちなんてあるの?」
これまでの常識では、爬虫類は単純な本能行動しかせず、感情や気分を持たないと考えられてきました。
しかし、最新の認知行動研究で、リクガメ(Red‑footed Tortoise, 学名 Chelonoidis carbonaria)にも“長期的な気分(ムード)”がある可能性が示されました。
この発見は、動物福祉の観点だけでなく、脊椎動物の認知・感情進化の理解にも大きな示唆を与えます。
本記事では、この研究のポイントと意義を3つの観点から解説します。
1. 認知バイアス(Cognitive Bias)とは?
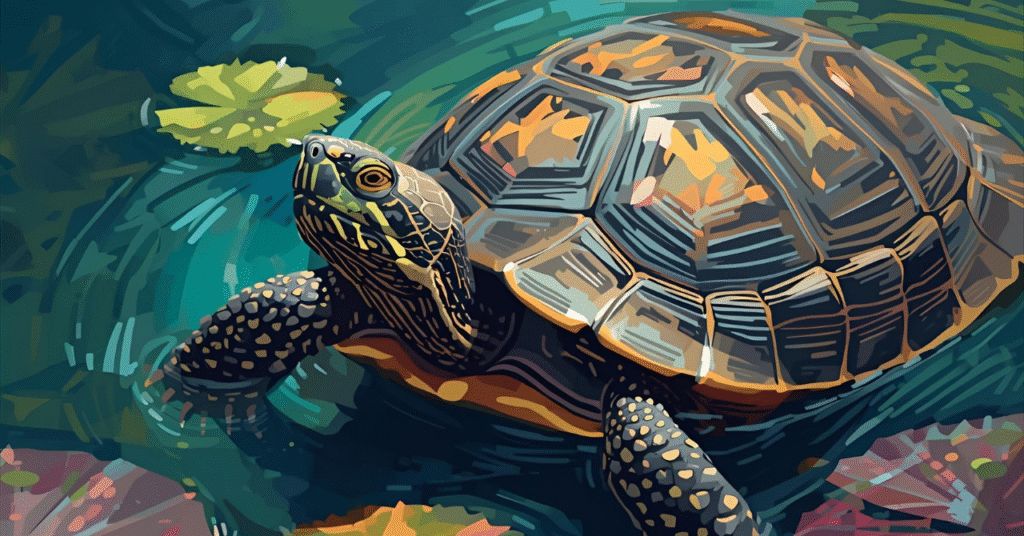
研究で使われた手法が「認知バイアス・テスト」です。
🔹概要
- 動物に曖昧な刺激を提示し、その反応を観察する
- 「楽観的/悲観的」な判断を示すかで、個体のムード状態を推定
この手法は、イヌやサルなど哺乳類では広く使われていますが、爬虫類での実施例はほとんどありませんでした。
2. 実験の方法:リクガメに“気分”を測定

研究チームは、15匹のリクガメを2種類の飼育環境で比較しました。
- 豊かな環境(Enriched environment):隠れ家や遊具、変化のある空間
- 標準的な環境(Standard environment):基本的な飼育スペースのみ
その後、曖昧な刺激(例えば、中間の色の物体)に対する反応を観察しました。
🔹結果
- 豊かな環境で育ったリクガメは、曖昧な刺激に対してより楽観的に判断
- 新しい物体や空間に対しても不安反応が少ない
- 標準環境で飼育された個体は、より慎重で悲観的な反応を示す
つまり、環境によってリクガメの判断傾向=ムード状態が変化することが示されました。
3. なぜ爬虫類にもムードがある可能性があるのか
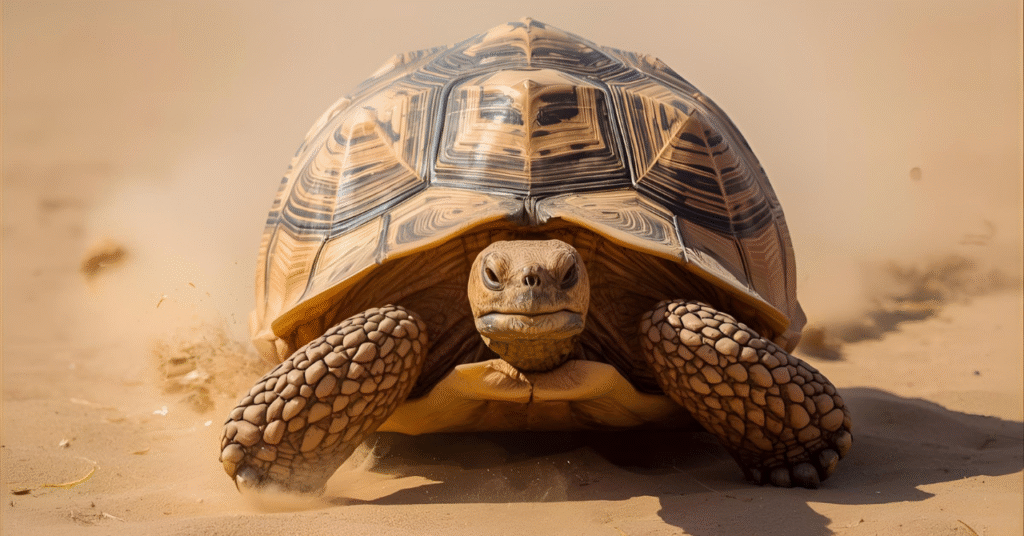
従来、爬虫類の行動は単純な本能反応と考えられていました。
しかし、今回の結果は以下を示唆しています。
- 脊椎動物における感情や気分の進化は哺乳類・鳥類だけに限定されない
- 爬虫類も環境や経験によって行動傾向を変化させる能力を持つ
- すなわち、彼らの脳にも「長期的な心理状態」が存在する可能性
これは、動物福祉や飼育方法に大きな影響を与えます。
4. 動物福祉への示唆

この研究の結果から、爬虫類を扱う際に次のような配慮が重要となります。
- 飼育環境を豊かにすることで、楽観的で健康的な行動を促す
- 爬虫類もストレスや不安を感じやすいことを理解する
- 動物園や保護施設での展示・飼育設計の改善に活かせる
従来、爬虫類は「感情を持たない」とされていたため、
環境の変化や刺激に無関心な設計が多かったのですが、
今回の知見はその前提を見直すきっかけになります。
5. 研究の意義:認知と意識の進化

爬虫類にムードのような心理状態があることは、進化的にも興味深い発見です。
- 哺乳類・鳥類だけでなく、爬虫類にも情動に関連する脳機能が存在する可能性
- 脊椎動物の認知・感情の進化を考える上で、より広範な視野が必要
- 動物行動学や神経科学における、**「意識の進化のパズル」**の一部として位置付けられる
6. 今後の課題と展望
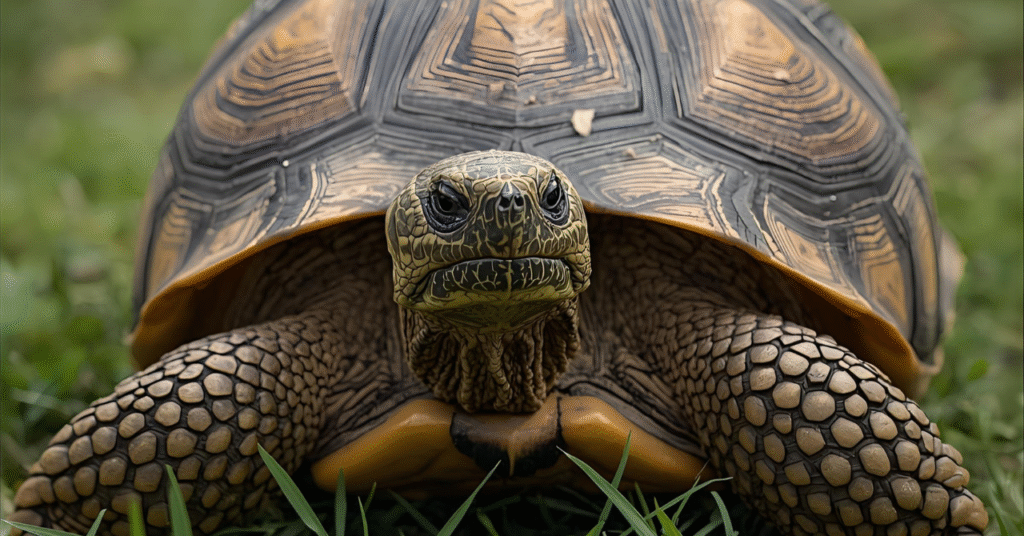
この研究は規模が小さく(15匹)、また特定のリクガメに限られています。
そのため、すべての爬虫類に当てはまるとは言えません。
しかし、以下の課題を踏まえることで、研究の可能性は広がります。
- より多くの個体・種での認知バイアスの実施
- 長期観察によるムードの変化追跡
- 他の環境要因(温度・社会的要素)との関連の解析
将来的には、爬虫類の心理状態を理解することで、より適切な保全・飼育法の開発につながると期待されます。
まとめ
- リクガメに“ムード”のような長期的心理状態が存在する可能性が示された
- 豊かな環境で育った個体は楽観的な判断傾向を示す
- 爬虫類の感情・認知の進化に新たな知見を提供
- 動物福祉や飼育環境設計に応用できる可能性
爬虫類も、私たちの思っている以上に「感じ、考える」存在なのかもしれません。
参考文献・出典
- プラズマ.org: “Cognitive bias in red-footed tortoises suggests mood-like states”
- Animal Cognition Journal 2025年版
- 動物福祉における認知行動研究のレビュー


