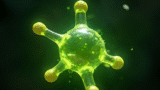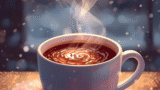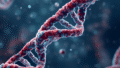朝食を抜くべきか、毎朝きちんと食べるべきか――この問いは長年議論されてきました。一方で、朝食欠食は「断続的断食(Intermittent Fasting)」の一種としてケトン体を高め、代謝・認知機能に良い影響を与えるという主張も注目されています。
しかし、疫学研究では「朝食を抜く人は病気のリスクが高い」ことも報告されています。
結論はシンプルです:
“個人差”と“目的(痩せたいのか、集中したいのか、健康維持か)”によって最適解は変わる。

ケトン体に関するまとめ記事はこちら!ケトン体のみならず、関連する遺伝子などの様々な内容を統合しています!
1.朝食を抜くと体内で何が起きるのか(代謝の変化)

朝食を抜くことは、夜間の絶食時間を延長することと同じです。これによって代謝は以下のように段階的に変化します。
● 食後(0〜数時間)
- 血糖上昇 → インスリン分泌
- 肝グリコーゲン合成
- 余剰分は脂肪に回る
● 断食中(6〜24時間)
- 血糖維持のためインスリン低下
- 肝グリコーゲンが枯渇していく
- 脂肪酸の利用が増加
- 肝臓でケトン体生成(ケトジェネシス)が開始
一般的に、12〜24時間で“代謝スイッチ”が入るとされます(個人差あり)。
絶食中に活性化するシグナルとして:
- AMPK
- SIRT1
- オートファジー
などが知られ、細胞修復やストレス耐性と関係します。
2.ケトン体とは何か 「エネルギー」と「シグナル」両方の顔を持つ
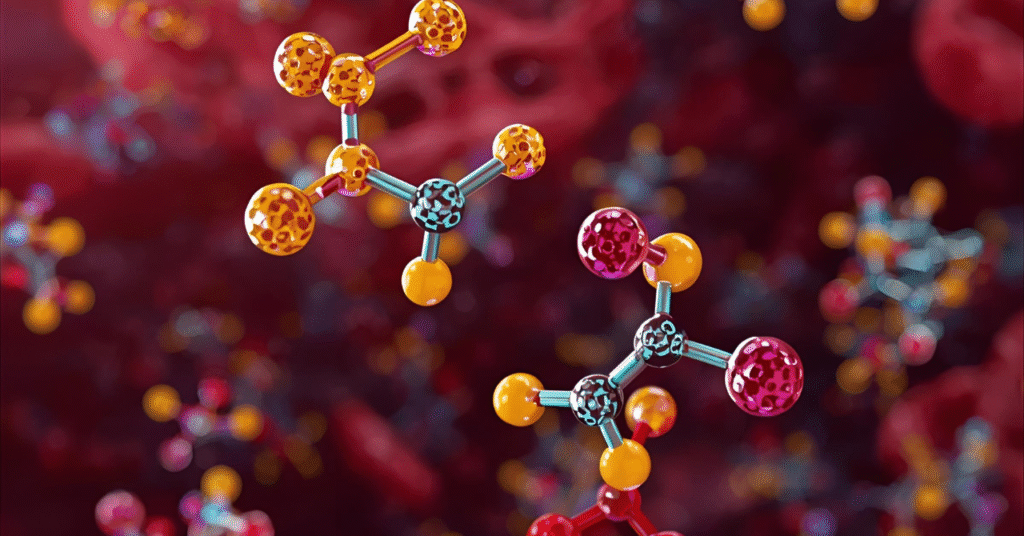
ケトン体(β–ヒドロキシ酪酸=BHB、アセト酢酸など)は肝臓のミトコンドリアで脂肪酸から作られます。
● エネルギー源として
- 肝臓から血中へ
- 脳・筋肉でアセチルCoAになりATPを生成
- 長時間の絶食では脳の主要燃料の一部に
● シグナル分子として
BHBは以下に影響すると報告されています:
- ヒストンの脱アセチル化(エピジェネティック調整)
- NLRP3炎症経路の抑制
- 抗酸化応答の促進
- 神経細胞の興奮性調整
つまり単なる燃料以上の生理作用があるということです。
3. 朝食欠食は不健康なのか?(疫学研究の結論)
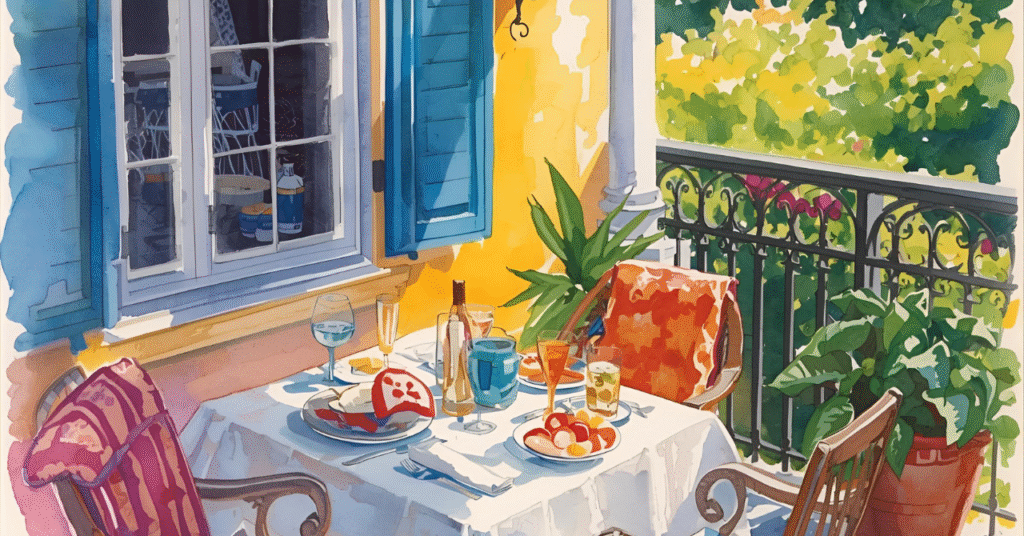
多数の観察研究では、
- 朝食を抜く人ほど心血管疾患リスクが高い
- 総死亡率も高い
と報告されています。
しかし重要な注意点があります。
● 交絡(confounding)
朝食を抜く人は以下の傾向が多い:
- 喫煙・運動不足
- 夜間の過食
- ストレス
- 社会経済的要因
● 逆因果
体調不良 → 食欲低下 → 朝食を抜く、という可能性もある。
● 朝食の“質”を見ていない
ポテチと菓子パンの朝食と、卵+ヨーグルト+果物では全く違います。
👉 朝食欠食が悪い、ではなく「どんな生活の中で朝食を抜いているか」が重要。
4. 朝食抜きで期待されるメリット6つ(科学的根拠つき)

① 体脂肪の利用が進みやすい
インスリンが下がり脂肪動員が進むため、短期的には体重が減りやすい。
② インスリン感受性が改善しやすい
特に肥満傾向の人で空腹時インスリンが下がることがある。
③ ケトン体による神経保護
BHBは神経のストレス耐性・炎症抑制に寄与する可能性。
④ オートファジーの活性化
細胞の清掃システムが働き、ミトコンドリアのメンテナンスに関与。
⑤ 代謝柔軟性(metabolic flexibility)が向上
脂質と糖の切り替えが円滑に。
⑥ 腸内環境のリズム調整
断食時間がマイクロバイオームの昼夜リズムに影響。
5. 朝食を抜くリスク・向かない人
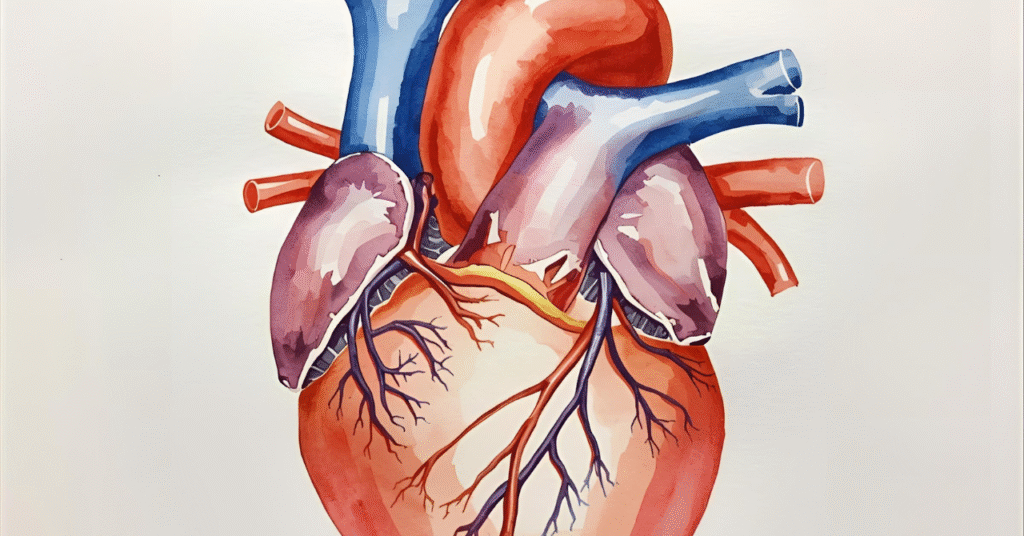
以下のグループは注意または非推奨。
- 糖尿病(特に薬使用者)
- 妊娠・授乳中
- 成長期の子ども
- 摂食障害の既往
- 低体重・高齢者
- 心血管リスクが高い人
また、朝食を抜いた後に暴食するケースは代謝にとって逆効果。
6. 実践ガイド(安全にケトン体を上げる方法)

● 初級:12時間断食
例:20時〜翌8時。まず1〜2週間。
● 中級:16時間断食(16:8)
もっとも一般的。朝食を抜くスタイル。
● 上級:24時間断食
医療管理下でのみ推奨。
測定すると良い指標
- 空腹時血糖
- 血中ケトン(0.5〜3.0 mmol/Lが目安)
- 体重・体脂肪
- 集中力や気分の変化
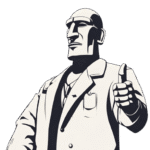
私は、朝食にプロテインを取り入れています。コスパや味を重視しているので、メーカーなどにはあまりこだわっていませんが、こちらを飲んでいます。おすすめは、ピュアココアも一緒に摂取することですね。
7. 朝食を抜く場合でも「食事の質」が最重要

- 摂食ウィンドウ最初の食事は高タンパク+食物繊維
- 電解質(ナトリウム・マグネシウム)補給
- 適度な運動を合わせると効果が安定
まとめ:朝食抜きの“正解”は目的と体質で変わる
- 短期的にはケトン体上昇・減量・代謝改善が期待できる
- 一方で、疫学研究では健康リスクとの関連も報告
- 大事なのは「目的」と「生活全体の文脈」
無理せず、客観データを取りながら試すことが最も安全な方法です。

個人差は大きいですが、結局は栄養バランスが良い食事が基本となっています。多少知識は必要ですが、栄養バランスについて学びたい方はこちらをどうぞ。
基礎的な部分はこちらでカバーできると思います。
参考
- Chen H, et al. Association between skipping breakfast and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis. (2020) PubMed.
- StatPearls — Physiology, Fasting (2023).
StatPearls — Biochemistry, Ketogenesis (2023). - Reddy BL, et al. Review Article: Health Benefits of Intermittent Fasting (2024). PMC.
- García-Rodríguez D., et al. Ketone Bodies in the Brain Beyond Fuel Metabolism (2021). Frontiers in Molecular Neuroscience.
- Qi J., et al. Beta-Hydroxybutyrate: A Dual Function Molecular and … (2022). PMC.
- Anton SD, et al. Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying the Health Benefits of Fasting (2017). PMC.