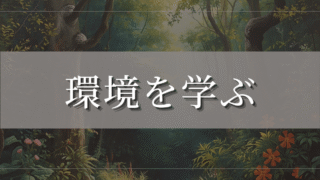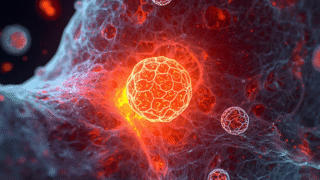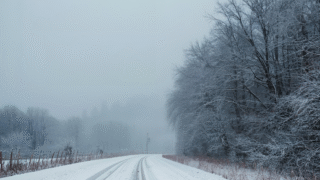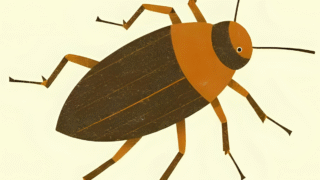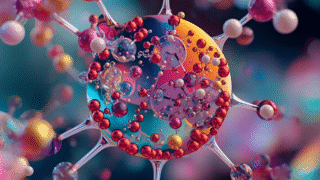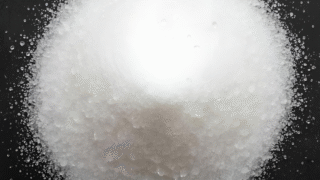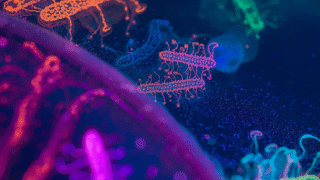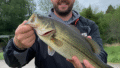はじめに:都市は「自然がない場所」ではない
「都会に自然なんてない」と思っていませんか?
実はその認識、ちょっと違います。
ビルの谷間やアスファルトの隙間、公園の小さな池や夜の街灯…。そこには意外にも多様な生き物が暮らしていて、人間が作り出した環境に適応して進化を続けています。
この分野を研究するのが「都市生態学」。
今回は、普段の生活の中で気づかれない 都市の小さな生き物たちの戦略 を紹介します。
1. アスファルトの隙間から現れる「雑草の王者たち」

街を歩けば必ず見かけるドクダミやオオバコ。
「あれってどこから生えてくるんだ?」と思ったことありませんか?
オオバコは特に面白くて、人に踏まれるほど発芽しやすい性質を持っています。アスファルトの隙間に生えるのは偶然ではなく、「踏まれることに進化的に適応」しているんです。
オオバコは昔、薬草としても使われていました。都市の雑草は「邪魔者」でありながら「生き残りの達人」でもあるのです。
2. 夜の主役は街灯?光に翻弄される昆虫たち

夏の夜に街灯へ群がる蛾やカナブン。実はこれ、生態学的にはかなり深刻な問題です。
昆虫はもともと月明かりを目印に移動する習性を持っています。しかし街灯の人工光が強すぎて方向感覚を失い、結果的に都市で「光トラップ」にかかってしまうんです。
近年ではLED照明がさらに強い影響を与えることがわかってきており、夜行性の受粉昆虫(ガなど)が減少 → 都市の植物の繁殖にも影響が出ていると指摘されています。

「街の明かり=おしゃれ」じゃなくて、実は 都市の生態系を変える要因 なんです。
3. カラスとハトは都市の勝ち組?

都市の鳥といえばカラスとハト。彼らはなぜこんなに多いのでしょう?
- カラス:ゴミ収集日の時間を覚えるほどの知能。都会の「時間割」に合わせて行動。
- ハト:人間が残したパンくずやポップコーンを餌にする柔軟性。
面白いのはツバメ。昔は川の崖に巣を作っていましたが、今はビルや家の軒下に巣作りをすることが多いです。人間の近くに住むことで、外敵(ヘビや猛禽類)から守られるという「ちゃっかり戦略」をとっているのです。
👉 カラスやハトを「都会の迷惑者」と思うかもしれませんが、実は 都市の最適解を選び抜いた進化の成功者 なのです。
4. 地下世界:下水道の知られざる生態系

普段はあまり気にしない下水道。ここにも独自の生態系が広がっています。
- ドブネズミ(定番の住人)
- カビや細菌
- 線虫や微小な昆虫
さらに、抗生物質が流れ込むことで「薬剤耐性菌」が生まれる場所にもなっています。つまり都市の下水は、ただの汚水ではなく 進化のホットスポット でもあるのです。
5. 公園は孤立した島?メタ個体群の視点

都市の緑地は小さな公園や街路樹など、点在する「緑の島」に分断されています。
生態学では、こうした断片化した環境を「メタ個体群」で説明します。簡単に言えば、ひとつの公園に残された昆虫や小動物は、近くの公園や緑地から仲間が来ないと絶滅してしまうのです。
都市で街路樹や緑道を整備するのは、単に景観を良くするためではなく、生物の「移動ルート」を作るために重要なんですね。
6. 未来の都市は「共生デザイン」がカギ
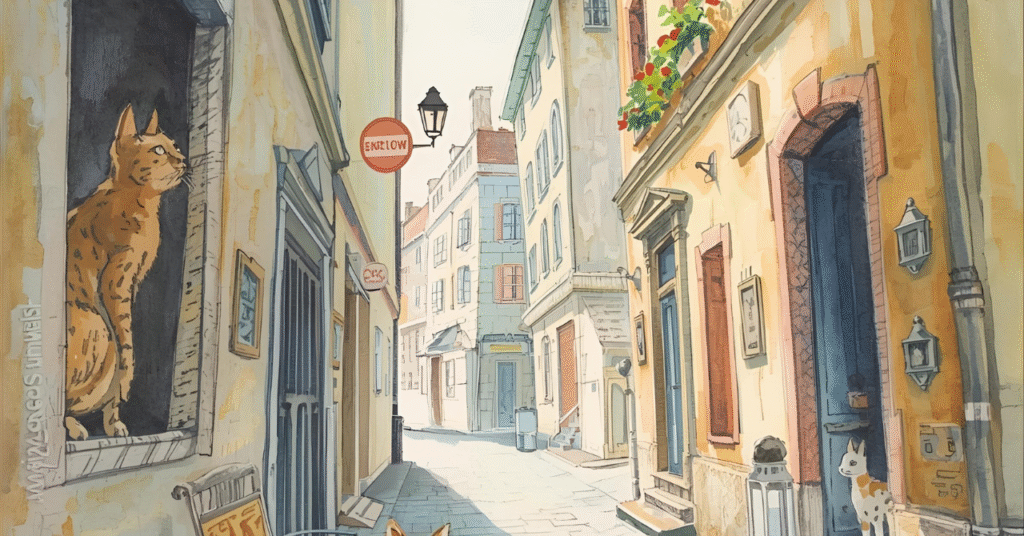
これからの都市づくりは、自然を排除するのではなく「共生」を前提にする必要があります。
- 屋上緑化で昆虫や鳥の拠点を増やす
- ビオトープを設けて水辺の生物を呼び戻す
- 光害を減らす街灯デザイン
これらは環境保全のためだけでなく、都市の住み心地を良くすることにも直結します。
都市生態学は、「未来の街をどう作るか」に直結する学問なのです。
おわりに:都市はもう一つの「自然」
街を歩くとき、ただの雑草やカラスの群れだと思っていたものが、実は都市の生態学的ドラマの一部だとわかると、風景がまったく違って見えてきます。
都市は人工物の集まりであると同時に、人と生き物が共に進化する舞台 でもあります。
次に街灯に群がる虫や、公園の片隅に咲く雑草を見かけたら、ちょっと足を止めて観察してみてください。そこには「都市という自然」の物語が隠されています。