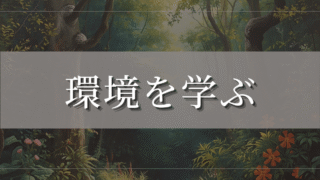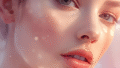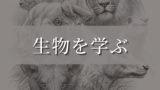はじめに
「いい音」とは主観的で人それぞれ違いますが、音響学・生理学・計測技術の視点から見ると、**“いい音に寄せるための共通項”**は見えてきます。本記事では科学的根拠や計測の観点を交えながら、イヤホン(ヘッドホン/IEM含む)で「いい音」を感じるための重要ポイントを7つに整理します。オーディオ好きも、これから買う人も使えるチェックリスト付きです。ですます調で読みやすく書きます。
1.周波数特性(フラット=良い?)と「ターゲットカーブ」

- イヤホンの**周波数特性(Frequency Response)**は最も基本的な指標です。低域〜高域の出方(増減)が音の「色付け」を決めます。
- 研究としては「多くのリスナーが好む周波数特性(Harmanターゲット)」が提案されており、メーカーや音作りの指標として広く参照されています。Harmanの実験では、多数の被験者がある特定のターゲットに近い応答を好む傾向が示されています。
- ただし「どの音量で聴くか(等ラウドネス特性)」によって理想の特性は変わります。等ラウドネス曲線(Fletcher–Munson / ISO226)が示すように、人間は周波数によって感じる大きさが違うため、同じ周波数特性でも音量によって“良さ”の印象が変わります。
実践アドバイス
- 試聴では同じ曲を複数の音量で確認する(小音量で低域が消えすぎないか/大音量で耳が疲れないか)。
- メジャー曲・生音系・自分の基準曲の3ジャンルで周波数バランスを確かめる。
2.「耳」とのカップリング:耳道共鳴・イヤーピース・装着感
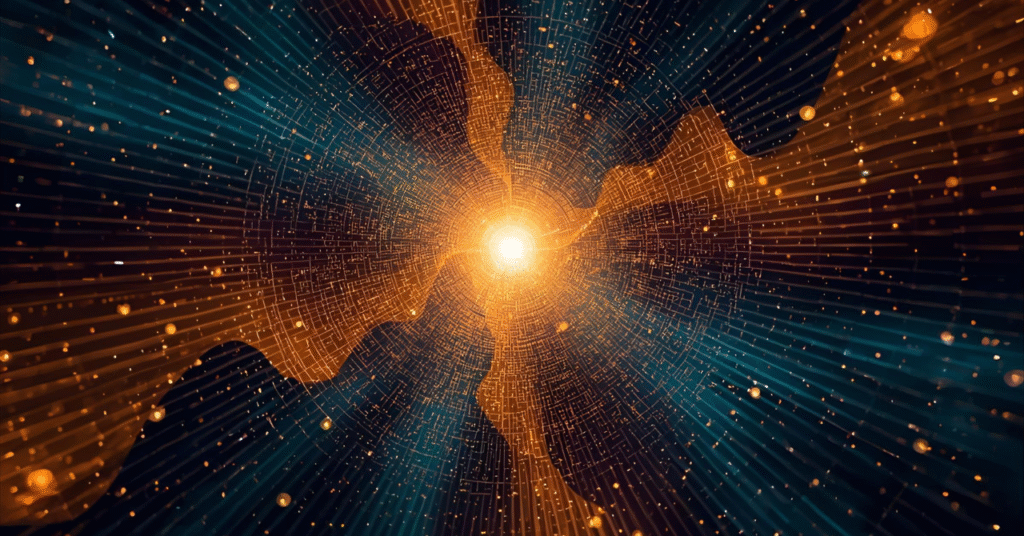
- 人の耳(外耳+耳道)は特定帯域(おおむね約2〜5kHz付近)を強調する性質があり、これが声や定位の明瞭さに直結します。HRTFや耳道共鳴の知見が示す通り、個人差と耳の形状による影響は大きいです。
- インナーイヤー(IEM)ではイヤーピース(シリコン・フォーム・ハイブリッド)や挿入深度で低域の量感やピークの位置が変わります。測定や再現性を重視するための規格(IEC 60318-4 等)や専門的な耳シミュレータも存在します。実際の測定では挿入深度や密閉具合が結果を左右します。
実践アドバイス
- IEMは必ず異なるサイズ・素材のチップを試す(フォームで低域が増す、シリコンで定位がシャープになる等)。
- オーバーイヤーはイヤーパッドの素材や密閉性で低音の量感と響きが変わるため、パッド交換で改善することが多い。
3.ドライバー(トランスデューサ)の種類と音の性格
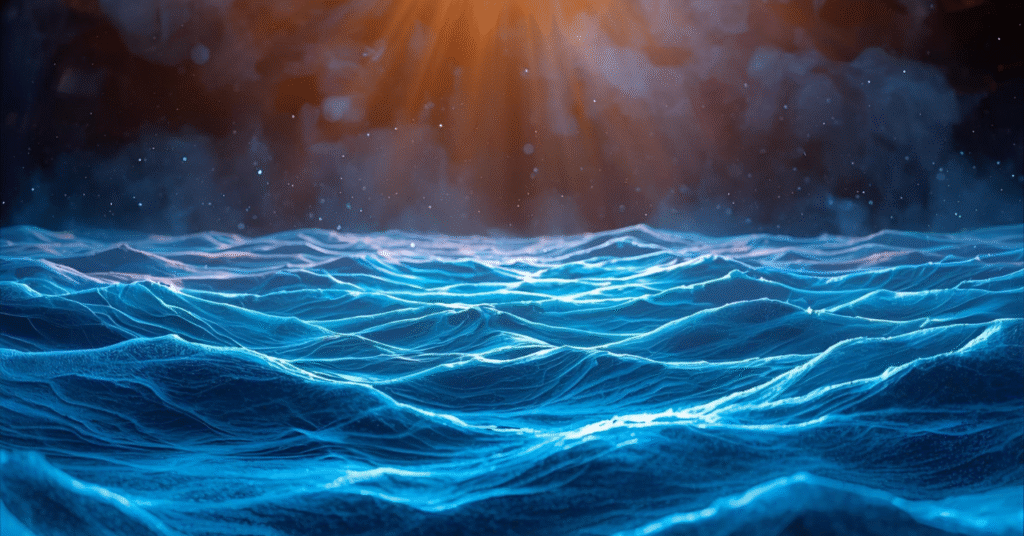
- 主なドライバーはダイナミック(コイル)/プラナー(平面磁界)/エレクトロスタティック/バランスド・アーマチュア(BA)などです。各方式は物理的特性が異なり、低歪み・トランジェント(立ち上がり)・レスポンスの差として音に現れます。プラナーやエレクトロスタティックは一般に低歪みで高解像、ダイナミックは能率・低域の押し出しに優れる傾向があります。
実践アドバイス
- 「厚い低音」「ライブ感」を求めるならダイナミックや大口径ドライバー、「分離・解像」を求めるならプラナー/エレクトロスタティックも検討する。
- 実際の音はチューニング(クロスオーバー、ポート設計)で大きく変わるため、ドライバー種だけで一概に判断しない。
4.歪み(THD)・群遅延・インパルス応答が与える印象

- **総高調波歪み(THD)**は測定ではよく使われますが、単純なTHD数値と聴感の相関は必ずしも強くありません。どの帯域でどの高調波が出るか、マスク効果(他の音に埋もれて聞こえにくくなる)などを考慮した評価が重要で、最近は知覚ベースの評価法が提案されています。
- 群遅延(group delay)や位相特性はトランジェントや音像の立ち上がり(いわゆる“キレ”や“スピード感”)に影響します。ある種の群遅延は聴感上で時間的なぼやけを生じさせるため、特に打楽器やアタックが重要な音楽で差が出ます。
実践アドバイス
- メジャーな試聴素材(スネア、ピアノのアタック、ボーカルの息づかい)で瞬発力と歪みをチェックする。
- メジャーな測定結果(周波数特性に加えインパルス応答や歪み)を公開しているレビューを参考にすると客観評価と主観評価のバランスが取れます。
5.サウンドステージと定位(HRTF・バイノーラル処理)

- ヘッドホンは左右のスピーカーから直接耳に音を入れるので「音が頭の中から出る」と感じやすいです。人間の空間定位はHRTF(頭部・耳のフィルタ)に依存するため、個別のHRTFを再現するDSP処理をすると外に抜ける(外在化)自然な定位感が得られます。これを利用したバイノーラルや空間音響技術は音場のリアリティに大きく寄与します。
- また、リバーブや初期反射の処理(precedence effect/先行効果)も「広がり」を決める心理的要素です。
実践アドバイス
- 映像やゲーミング用途では専用の空間処理(WindowsのSpatial Audio、各社のバーチャルサラウンド、個人用HRTF)を試す価値があります。
- 音楽では「定位が中央にまとまるか」「左右の広がりが自然か」を自分の基準曲で確認する。
6.ワイヤレス(Bluetooth)時代のコーデックと遅延・圧縮

- ワイヤレスでは**コーデック(SBC・AAC・aptX系・LDACなど)**によって伝送可能なビットレートや遅延が変わります。高ビットレート(LDAC等)や可変ビットレートを持つコーデックは理論上高音質を保ちやすく、遅延の小さいコーデックは映像同期(動画・ゲーム)で有利です。なお実際の品質は端末・OS・実装状況に左右されます。
実践アドバイス
- ハイレゾやロスレス志向ならコーデック対応を要確認(送信側と受信側両方)。
- ゲームや映画用途なら低遅延コーデック(aptX LL系など)を優先する。
7.マイナーだが重要:ケーブルのマイクロフォニクス、ブレークイン議論、耳の健康

- マイクロフォニクス(microphonics):ケーブルが衣服や体に擦れる振動がイヤホンに伝わると雑音になります。ケーブル被覆や取り回しで大きく改善できます。
- ブレークイン(burn-in):ドライバの物理的変化を主張する声もありますが、科学的には「ドライバ自体の可聴上の変化は小さい/不確定」「耳やパッドの慣れ(脳の適応)が主因」の説が有力です。最も実用的なのは「長く使って慣れる」ことと「パッド/チップなど物理的要素の経年変化」を分けて考えることです。
- 耳の健康(聴覚保護):音の良さは大きな音で得られるわけではありません。WHOやNIOSH等のガイドラインは、安全な音量と時間(例:85dBAを基準に8時間等)を示しており、長時間の大音量は不可逆的な聴力損失を招きます。安全に楽しむことが根本の“いい音”です
実践アドバイス
- マイクロフォニクスが気になる場合はケーブルを替えるか、服にクリップで固定する。ワイヤレスならこの問題は小さい。
- 長時間リスニング時は音量を下げる、適度に休憩する(60/60ルール等の目安を利用)。
結論:イヤホンの「いい音」を決めるチェックリスト(7選)
- 周波数バランス:Harmanターゲットや自分の基準曲での音のバランスを確認。
- 装着とシール:IEMはチップを替えて最良のシールを探す(低域は特に影響大)。
- ドライバー種:用途(低音重視/解像重視)に合わせてドライバーを選ぶ。
- 歪み・トランジェント:スネアやピアノのアタックで“キレ”をチェック。
- 音場・定位:バイノーラル・HRTF処理や開放/密閉の違いを試す。
- 接続品質:有線かワイヤレスか、コーデックと遅延を用途で決める。
- 耳の安全と実用性:大音量に頼らず長く楽しめる選択をする(WHO/NIOSH基準を参照)。
まとめ(購入前・試聴時の実用チェック)
- 基準曲を3種類(自分の好きな曲+基準となる試聴曲)用意する。
- 同じ曲を小音量・中音量・大音量で聴き比べる(低音の厚み、耳疲れ、定位)。
- IEMはチップを必ず複数試す。オーバーイヤーはパッドの素材も確認。
- ワイヤレスは送受のコーデック対応を確認する。ゲーム用途なら低遅延優先。
- 聴覚保護(音量と時間)を守る。良い音は“長く楽しめること”が大前提です。
参考
- Olive, S. E.「The Perception and Measurement of Headphone Sound Quality: What Do Listeners Prefer?」(Harman関連まとめ) — ListenInc PDF.
- Equal-loudness contour / ISO226(Fletcher–Munson 等の等ラウドネス基準、周波数感度) — Wikipedia(概説)。
- GRAS — IEC 60318-4(耳シミュレータ)製品情報(耳と測定の関係)。
- AES / 研究論文:歪みの可聴性とヘッドフォン評価に関する研究(歪み指標の課題)。
- HRTF(Head-Related Transfer Function)解説(定位・外在化の基礎)。
- Bluetooth / コーデック解説(SBC・AAC・aptX・LDAC 等の比較) — SoundGuys 等の解説記事。
- WHO「Safe listening(耳の健康)」:長時間聴取の安全基準と推奨。
- イヤホンのチップ・耳道ジオメトリや測定の詳細(GRAS ear canal white paper) — 耳道形状が周波数特性に与える影響。
- ブレークイン議論の概説(SoundGuys / Audio Science 等の立場) — 科学的な見解と実用的助言。