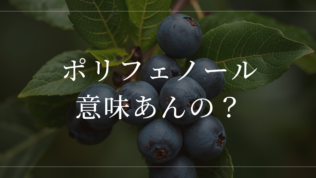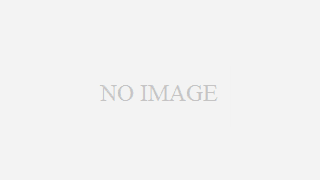 植物
植物 【保存版】フラボノイドの生物学的作用7選|知られざる進化的役割と健康効果を徹底解説!
フラボノイドと聞くと、「抗酸化作用」「ポリフェノールの一種」といった健康寄りのイメージを持つ人が多いと思います。しかし近年、フラボノイドは植物の生態・進化・ストレス応答と密接に関わる非常に重要な生理活性物質であることが分かってきています。本記事では、一般的な効果だけでなく、**生物学的・生態学的に見た“フラボノイドの本質”**を分かりやすく解説します。フラボノイドを理解すると、・植物がなぜ紫外線に強いのか・なぜ昆虫は特定の植物を好むのか・食品の色や味がなぜ多様なのかが一気にクリアになります。さらに、私たち人間にとっての健康効果も「なぜその作用が起こるのか」という仕組みから理解できるようになります。