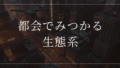夜の街灯や家の明かりに群がる昆虫の姿は、誰もが一度は目にしたことがある光景です。この現象は「人工光に引き寄せられる」として広く知られていますが、その背後には複雑なメカニズムが隠れています。昆虫がなぜ光に集まるのか、これまでに多くの仮説が提案されてきました。本記事では、これらの仮説を解説し、最新の研究成果や関連知識を交えて、光が昆虫に与える影響について深く掘り下げます。
昆虫は紫外線が見える!

昆虫が頻繁に集まってくる電灯には、紫外線が放出されており、昆虫たちはその紫外線を感知し、飛来しているといわれています。ほとんどの街頭はLEDが採用されています。LEDはほとんど紫外線が放出されないため、集まる昆虫は少なくなります。そのため、昆虫を集めるためには紫外線が放出される白熱電球などを用いる場合が多いです。昆虫を集める方法には、紫外線が出るライトと、光を反射しやすい白色の布を用意して採集する灯火採取(ライトトラップ)というものがあります。

人間には紫外線が見えませんが、昆虫は、紫外線が見える代わりに赤が見えないみたいです。
昆虫が光に引き寄せられる理由に関する主な仮説

昆虫が光に集まる現象を説明するために、以下の仮説が挙げられています。これらを順に見ていきましょう。
1. 安全な隠れ家の誤認:隙間への逃避仮説
自然界では、昆虫は捕食者から身を守るために隙間や洞窟など暗く狭い場所を避難所として利用します。この仮説では、人工光が背景の暗闇との対比によって「隙間」と誤解され、昆虫が光に向かう行動を取ると考えられます。たとえば、蛾がライトの近くでじっとしている姿は、隠れ家を見つけた際の行動に似ています。

昆虫の視覚は、人間の目とは異なり、光の強度差を敏感に感じ取る能力があります。この特性は彼らの生存戦略において重要です。しかし、人工光が自然の光環境を歪めることで、彼らの認識能力が混乱し、適切な安全行動が取れなくなる可能性があります。
2. 月を基準にしたナビゲーション:月光コンパス仮説
多くの飛行昆虫は、月光を基準に一定の角度を保ちながら飛ぶ「月光コンパス」を利用しています。この仮説では、人工光を月光と誤認し、一定の角度を維持しようとする結果、光源の周囲を螺旋状に飛ぶ行動が生じると説明されます。

昆虫が月光を利用する能力は、捕食者を避けたり、繁殖地を見つけるための進化的適応と考えられています。しかし、人工光の普及により、この進化的特性が逆に彼らを罠に導くこととなっているのです。特に蛍光灯や街灯が繁殖期の昆虫に与える影響は、生態系全体に広がる可能性があります。
3. 熱への魅力:熱放射仮説
炎や白熱灯は光だけでなく熱も放射します。一部の昆虫は熱を食物や交尾相手の存在と関連付けるため、熱を伴う光源に引き寄せられる可能性があります。この仮説は、蚊が人間の体温を感知して近寄る行動とも関連しています。

昆虫は紫外線や赤外線の一部を感知する能力を持つ種がいます。この感覚が人工光源に反応することで、特定の光に惹きつけられる行動が起こる可能性があります。特に農業害虫に対する赤外線ライトの利用は、害虫駆除の新たな手法として研究されています。
4. 視覚の混乱:眩惑仮説
昆虫の目は微弱な光に適応しており、夜間に活動する昆虫は特に明るい光に敏感です。強い人工光は昆虫の視覚を混乱させ、飛行の制御が難しくなることがあります。この結果、光源の周囲を不規則に飛び回る行動が見られます。

「光害」と呼ばれる人工光による環境汚染は、昆虫の行動や生息地に深刻な影響を与えています。たとえば、光害の強い地域では、昆虫の繁殖や餌探しが妨げられることが観察されています。これは鳥やコウモリなどの昆虫を捕食する生物にも影響を及ぼします。
新たな研究で明らかになった知見

最近の研究では、最新のモーションキャプチャ技術を用いて、昆虫が人工光にどのように反応するかを3次元で解析しました。その結果、以下の新たな知見が得られました。
1. 昆虫の飛行パターンの分類
研究では、昆虫が光源に対して以下のような3つの飛行パターンを見せることが明らかになりました。
- 軌道飛行:光源の周囲を円形に飛ぶ。
- 直進と急反転:光源に直進し、突然反転する。
- 回転的な停滞飛行:光源の周囲をゆっくりと旋回し、次第に動きを止める。
2. 背側光応答の影響
昆虫は自然環境では背中を光に向けて飛行する「背側光応答」を利用しますが、人工光ではこの行動が歪められ、不規則な飛行につながることが分かりました。
3. 光の波長による影響の違い
紫外線、可視光線、赤外線など、光の波長によって昆虫の反応が異なることが確認されました。たとえば、紫外線ライトは蛾を強く引き寄せる一方で、赤外線にはあまり反応を示しませんでした。

飛行するときに安定するために光を使っていたんですね。昆虫の背中には紫外線を感じ取る器官があるのでしょうか?
昆虫が集まらない光の波長

昆虫が光に集まる理由の一つは、光源が昆虫の視覚に強く影響を与えるためです。昆虫は紫外線や可視光線、赤外線など、特定の波長の光に敏感に反応します。昆虫が集まらない光には、以下の波長範囲の光が含まれます。
長波長の光(赤色や赤外線)
多くの昆虫は、紫外線や青色の光に特に強く反応しますが、長波長の光(赤色や赤外線)にはあまり反応しません。赤色や赤外線の光は、昆虫の視覚器官である複眼にはほとんど感知されないため、昆虫はこれらの光源に引き寄せられることが少ないとされています。例えば、赤色の光を使用した照明では、蛾やその他の夜行性昆虫はほとんど集まりません。

赤色光は昆虫が飛行や繁殖行動を行う際に必要とする視覚情報を提供しません。そのため、赤色光は昆虫が求める「誘引力」を欠いています。これを応用した技術として、赤色LEDライトを用いた害虫対策や、街灯の照明に赤色光を使う試みがあります。これにより、昆虫の集まりを減少させることができます。
緑色の光
緑色の光は、昆虫にとって比較的低い反応を示す光として知られています。多くの昆虫、特に昼行性の種は、緑色の光に対する感度が低いため、この波長の光源にはあまり集まらない傾向があります。緑色光が昆虫に与える影響は種によって異なりますが、一般的には紫外線や青色光ほど強い引き寄せ力を持っていません。

緑色光の利用は、農業や庭園における害虫駆除や誘引を制御するために活用されることがあります。例えば、害虫を避けるために緑色の光を使用した蛾の誘引装置や、観察用のライトに使用されることが増えています。
光源の性質による影響

昆虫が集まらない光の性質には、波長だけでなく、光源の特性(強度、方向性、フリッカー特性など)も関係しています。以下のような光源の特徴が、昆虫の引き寄せに影響を与えます。
低強度の光源
強い光源ほど昆虫は集まりやすいとされていますが、低強度の光源では昆虫の反応は鈍くなります。低強度の光や遠くの光源は、昆虫にとって認識しづらく、近づこうとする動機が減少します。このため、光源があまりにも遠く、または暗すぎる場合、昆虫はその光に引き寄せられることは少ないです。
輝度の均等な光源
強い光源でも、輝度が均等に拡散されていると、昆虫がその光に集まる可能性は低くなります。例えば、フラッシュライトやスポットライトのように、特定の場所を集中的に照らすタイプの光源は、昆虫が反応しやすいです。一方で、輝度が均等な蛍光灯のような光源には、集まりにくい傾向があります。
昆虫が集まらない光の応用例
昆虫が集まらない光を活用した技術や製品は、環境への影響を最小限にしながら、虫害を防ぐために広く使用されています。以下はその一例です。
街灯の変更
都市部や農地周辺で使用されている街灯の多くは、蛾やその他の夜行性昆虫を引き寄せる紫外線を多く放出しています。しかし、赤色光や黄色光を多く含んだLEDライトに変更することで、昆虫の集まりを減らすことができます。これにより、環境への光害を軽減し、昆虫の生態系に与える悪影響を抑えることができます。
農業における害虫防除
農業では、緑色や赤色の光を利用して害虫を避けるための方法が研究されています。例えば、緑色のLEDライトを用いた虫除け装置や赤色の光を使った農作物の保護などが行われています。これにより、農薬の使用を減らすことができ、より環境に優しい農業を実現するための手段となっています。